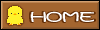人の話を聞くのは、簡単そうで難しいと思った。ここに来る人たちは、悩んでいるのだけれでも、結局、何もできない自分の無力さを感じる。 人の話を聞くのは、簡単そうで難しいと思った。ここに来る人たちは、悩んでいるのだけれでも、結局、何もできない自分の無力さを感じる。
私は、体調が優れず、辞職スレスレの状態で、ここに来れば、少し楽になれるかなと思った。悩んだら、あせらず、自分にとって、良いと思ったことをしてみるが良いと思う。
 松田さんのお話しは、大変参考になりましたし、その後のグループディスカッションも、議論が白熱して大変良かったです。 松田さんのお話しは、大変参考になりましたし、その後のグループディスカッションも、議論が白熱して大変良かったです。
 毎回いろいろな方がいらっしゃり、それぞれの悩みを話し合って、楽になったり、こんなにたくさんの人が苦しんでる状態ってなんなんだろうと不安になったり・・・。 毎回いろいろな方がいらっしゃり、それぞれの悩みを話し合って、楽になったり、こんなにたくさんの人が苦しんでる状態ってなんなんだろうと不安になったり・・・。
みんな早く抜け出せるといいです。
 いろいろ聞けて参考になりました。 いろいろ聞けて参考になりました。
 今の引きこもりの若い人が、どうなっているのかという事実を知れてよかったです。 今の引きこもりの若い人が、どうなっているのかという事実を知れてよかったです。
 「当事者の外から見えない部分(対人関係・感情)」に親や支援団体は目がいかない。 「当事者の外から見えない部分(対人関係・感情)」に親や支援団体は目がいかない。
不登校・引きこもりの子と親との関係に限らず、普通の親子関係・教師と生徒の関係・上司と部下の関係等にも言えることであると気付かされました。
(「上の者」は、「下の者」を社会に適応し、能率や流れを支えるようにさせるという役目を負っている以上)、「上の者」はどうしても「下の者」のそういう部分には目がいかないし、目がいってもどうすることもできないのが現状(現実)です。
しかも、本質的に「上の者」という立場と「カウンセラー」という立場とは、両立しないものです。
「人を育てる」という営みを行う者は、理性や幻想(やればできる・通じる等の精神論)で動くのでなく、しっかり飲みこんだ上で取り組み、実践を重ねるという基本姿勢が必要なのだと感じました。
これがないままの「人を育てる営みは必ず失敗するでしょう。
| | | | | |