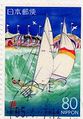カテゴリ:和歌山市(和歌山県)
和歌山市
周辺ニュース
◆(わかやま研究)子どもの貧困、現状と課題 食事や学習支援、途上 /和歌山県
県内の子育て世帯で、収入が生活保護基準以下の割合は17・5%に上る。
山形大の戸室健作准教授が2012年の統計をもとに計算した結果だ。
和歌山は47都道府県で9番目、近畿では大阪に次いで2番目に多い水準という。
「子どもの貧困」対策を国が政策課題とする中、世代を超えた「貧困の連鎖」は断ち切れるのか。県内の取り組みや課題を探った。
「わー、逃げろ!」。
3月24日夜、和歌山市楠見中の住宅に鬼ごっこをする子どもたちの声が響いていた。
週1回、夕方から開かれている「子どもの生活支援ネットワーク こ・はうす」の取り組みだ。
母子家庭の子どもらが和歌山大の学生らと夕食をともにし、勉強を教えてもらったり、一緒に遊んだりする。
この日は学生4人と小中学生5人がクリームシチューやサラダを食べた後、遊びに興じていた。
食卓を囲む楽しさや学ぶ喜びを伝えようと、社会福祉士の馬場潔子さん(47)や子育て支援の「きのくに子どもNPO」(和歌山市)などが昨年1月に始めた。
利用する6世帯のうち5世帯は母子家庭の子どもたち。
1回300円の食材費を払えば参加できる。
運営者の一人で和歌山大教育学部の谷口知美准教授(34)は「子どもには安心できる居場所となり、孤立しがちな親には心の支えになる」と話す。
中学3年になる男子生徒(14)は以前、「大学に行っても何も変わらない」と思っていたが、大学生と一緒にキャンパス見学をして進学したいと思うようになった。
この春、県立高に進学する女子生徒(15)は「受験でしんどい時はストレス解消になったし、テスト期間中は大学生に勉強を教えてもらえた」。
◇
低料金で食事を提供し、孤食をなくす「子ども食堂」といわれる取り組みは全国に広がるが、和歌山ではそうした活動は緒に就いたばかりだ。
県は新年度予算に「和歌山こども食堂支援事業」(200万円)を盛り込み、食事の提供などを行う民間団体に上限20万円を助成する。
だが、「こ・はうす」以外の活動はまだ把握していないという。
また、親から子どもへの「貧困の連鎖」を防ぐと期待される学習支援事業についても、目立った動きはみられない。
さいたま市のNPO法人「さいたまユースサポートネット」が昨秋にした全国調査で、県内で「実施中」と回答した自治体はなかった。
新年度からは田辺市が地元のNPO法人に委託し、退職した教員らが小中高生を対象に無償で学習支援をする予定はあるという。
◇
一方、そうした取り組みがあっても、条件が合わなければ利用が難しいのも実情だ。
和歌山市内の女性(34)は「こ・はうす」を見学したが、自宅から遠いために利用を諦めた。
夫と離婚後、女手一つで3人の子どもを育てている。
パートの収入は月14万円。
新年度は中学3年の長女と小学6年の次女が修学旅行に参加する。
小遣(こづか)いを含めると長女だけで6、7万円と出費はかさむ。
給食費などの就学援助や児童手当を受けているが、家賃などの支払いを済ませると手元にはほとんど残らない。
「高校受験を控える長女を塾に通わせたいが、数万円の月謝を考えると厳しい」
「生活を立て直せなかったら学力も上がらない」。
貧困世帯の子どもが多い和歌山市の小学校で教壇に立った経験がある男性教諭(58)はこう話す。
夜、働きに出る親の育児放棄(ネグレクト)もあった。
子どもは寝不足が常態化し、朝ご飯も食べていなかったため、毎朝、校長室で食事と睡眠をとっていたという。
「学びを定着させるためにも、子どもの居場所づくりは重要だ」と訴える。
□授業外の支援強化、地域で取り組みを
関西国際大学の道中隆教授(社会保障論)の話
私の調査では、生活保護を受ける世帯主の25%は、自ら育った家庭も生活保護世帯だった。
貧困の連鎖を断つには授業外の学習支援を強化し、子どもの進学や職業選択の幅を広げる必要がある。
子どもへの学習支援は社会的投資の効果が大きい。
地方でも行政が積極的に社会福祉協議会やNPOなどと連携し、学生ボランティアや教員OBなどの協力を得ながら地域を挙げて取り組んでほしい。
〔2016年4月12日・貧困ネット、平成28(2016)年4月4日 朝日新聞 大阪地方版朝刊〕
周辺ニュース
◆子どもシェルター:理解を 「今私たち大人にできること」現状や利用者の声紹介 桐蔭高生、創作劇も /和歌山
虐待などで安心して生活する居場所を失った子どもたちの緊急避難場所「子どもシェルター」への理解を深めるためのシンポジウム「子どもたちのSOS―今私たち大人にできること」が24日、和歌山市小松原通1の県民文化会館であった。
パネルディスカッションに加えて演劇も上演され、市民や福祉関係者らが熱心に見聞きした。
県内のシェルター「るーも」は2013年10月に開所。これまで10代後半の女子を中心に延べ29人を受け入れた。
子どもたちは平均2カ月の入居期間中、一般的な家庭を経験し、担当弁護士やスタッフらと共に児童養護施設や親元など次の行き先を一緒に探す。
パネルディスカッションでは、元児童相談所職員や担当弁護士らがシェルターの現状や利用者の声を紹介。
伊藤あすみ弁護士は「るーもに来る子どもは大人や社会への不信感が強い。
自分が大事にされているという実感が生きる力の回復につながる」と話した。
今後の課題としては、シェルター退所後のケアやスタッフの負担の軽減などが挙がった。
その後、県立桐蔭高演劇部が子どもシェルターについて学び脚本を手掛けた創作劇「seven-day prologue」を上演。
シェルターでの生活を通し成長していく主人公らを演じた。
〔2016年1月・貧困ネット、平成28(2016)年1月25日 毎日新聞 地方版〕
紹介する本はこちら⇒◎
カテゴリ「和歌山市(和歌山県)」にあるページ
以下の35ページがこのカテゴリに含まれており、そのうち35ページが表示されています。
いえきこしとなひふ |
ほむるれわ |
わ の続き |