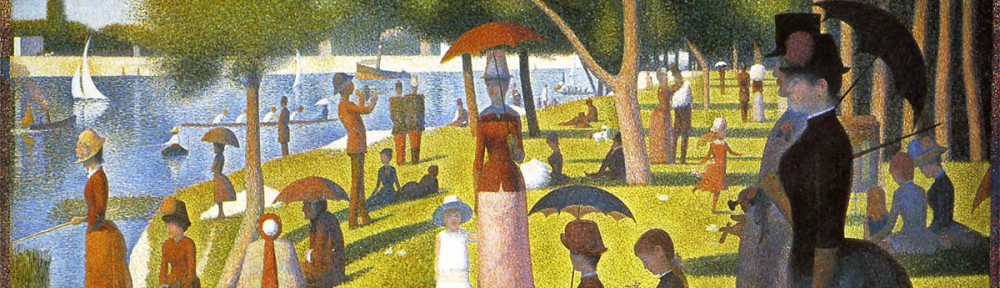3月23日までに43か所の保健所から情報提供をいただきました。目標(心積もり?)としては30か所程度からの情報提供を期待していましたので、この時点でそれをかなり上回る件数になり感謝しています。
回答するために問い合わせ等がいくつかあり、少なくともさらに数件の回答を期待できますので、50件に届くかもしれません。
全体としては関東・中部地域からの情報提供が少ないように思います。
質問事項にわかりづらいところが一つありました。
「対応状況(引きこもりと周辺状況)」としたところです。どういう人が支援対象になりますかの主旨ですが、わかりづらかったようです。回答していただいたところには「どういう方法で支援をしているのか」を答えていただいたところがあります。それらは「対応方法」として別項目を置いたのですが、重複して回答されたことになります。
問い合わせのなかでもこの部分の意味内容がわからないとされた方がいましたので、質問自体があいまいであったと思います。
回答は順次サイトに掲載しています。「保健所と引きこもり」として独自分類をしました。
これは「保健所」ページが既にあり、所在地や連絡先についてはおおよそ情報提供を終えているため別にしたのです。
月別アーカイブ: 2012年3月
若者の適応でなく企業の変化が必要
3月21日付けの2つのブログで不登校および引きこもりの増大に伴う学校の変化の一端を見てきました。それは子どもの変化によるものですが、その延長には若者の変化があります。若者の変化は社会においてどのように表面化するのでしょうか。その一つをみましょう。
内閣府から2010年春に大学、専門学校、高校、中学校を卒業した人の就職状況が発表されました。就職できなかった人と就職後3年以内の退職した人の割合が大学・専門学校で52%、高校で68%(いずれも中退を含む)となっています。就職し現在も勤務するのはその裏返しでそれぞれ48%、32%になります。卒業時点の就職率は推計で、大卒91.8%、専門学校卒87.4%、高校卒93.9%ですから、就職したあとの退職率の高さが目を引きます。
大学と専門学校の卒業生に絞ると、大学院などへの進学者を除くと77.6万人が卒業し、約7割の56.9万人が2010年春に就職しました。このうち19.9万人が3年以内に離職し、卒業後の無職やアルバイトが14万人。その年の中退者6.7万人を加えると、無職と安定した職についていない人が40.6万人、全体の52%になります。高校卒業生や中学卒業生の就職状況のうち無職などが68%、89%とさらに多くなります。
この背景には就職難があり、学生には適性に沿った就職先を選んでいる余裕がなかったことを指摘しなくてはなりません。しかし、私はそれより重大な要素があると考えます。情報社会に入りつつあるのです。3月8日の「引きこもりからの社会参加について(その3)」で私は情報社会をこう書きました。
「確立した情報社会はインターネットの普及だけにはとどまりません。社会関係、人間関係がフラットな関係(上下関係から等質な関係)に移行します。そこでは自己実現の条件が広がるとともに、その条件を提供できない社会や組織は衰退していくものと思われます」。
企業社会が若者の感性(フラットな人間関係ややりたいことを仕事にしたい)を受け入れられなくなっているのです。そのレベルでのミスマッチがすでに起きているのです。
毎日新聞の報道によると、政府はこれにたして学生が自らの適性や就きたい職業についていないとか就職のミスマッチを指摘し、「従来の雇用対策の練り直し」をするといいます。大学の在学中に職場での勤労体験をするインターンシップの推進、大企業志向の就職から採用意欲の強い中小企業への就職先の拡大、正規雇用の少なさ(要因として指摘はするが正規雇用の拡大は図らないらしい!)を考えるだけでは時代の変化をとらえていないのです。
私が政府の対応が時代をとらえていないと考えるのは不登校に対応した学校側の歴史からです。不登校生が増大したのは80年代の中ごろです。不登校の彼ら彼女らは学校への不適応として生まれたのですが、それは基本的には“適応”によっては解消されなかったのです。道ができたのは学校側の変化でした。
学校を変化させる内部からの力は全体として弱く、従来の学校の外側に不登校生を受け入れる各種の学校が生まれました。それがきわめて明瞭になっているのは高校です。
通信制サポート校が80年代の後半から生まれどんどん増えました。次に大検が高卒認定資格になりました。そして昼間定時制高校が生まれました。東京都のチャレンジスクールはその一つです。いずれも学校の内部から変えようとした動きによるものとはいえません。通信制サポート校の広がりの現状は、学習塾など学校以外の場がサポート校化したことです。
このような経過のなかでチャレンジスクールは、なかば役割を終えたように振舞い始めました。この意味することについてはすでに書きました。
企業社会においても同じことが異なる条件のなかで様相を変えて表われています。新卒就職者の早期退職とは、いくつかの複雑な事情かからみあい若者が既存の人間関係と社会ルールの継続する企業を拒否し始めたものなのです。もとよりその一因で退職者・非就職者の全体を説明するわけではありませんが、それを抜きにしては重要な時代的な背景をとらえていないのです。
子どもは時代の変化をいち早く察知し、極端に表現します。80年代なかばに目立ってきた子どもの不登校とは、この社会の大きな変化を無意識にとらえた行動と表現であることがここにきて改めて確認できるのではないかと思うのです。それに続いて若者の企業拒否が現われ始めました。企業社会はこれから徐々に変化を始めていくでしょう。それは情報社会への対応ともいえるのです。
チャレンジスクールが示すもの
考えていた本論に入る前にもう一つ別のことを書きます。高校入試の作文問題が考えさせてくれたことです。
東京都のチャレンジスクールという昼間定時制高校は、不登校生を受けいれるためのものでした。厳密に言うとそうではないというかもしれませんが、あまり強がらないでいただきたいのです。少なくとも不登校生が増えている状況での行政としての対応策であったわけです。
設立の初めから入学希望者は多く、平均競争率2倍以上は当然の状況でした。設立数年してもこの“人気”はつづき、学校としての認知も進みました。ここにきて軌道の微妙な修正を図っていると思えます。なかには不登校対応としての役割は終了に向かうと考えたい人もいるでしょう。あるいはまた私学とのやり取りへの対応策が含まれているかもしれません。私学に行く生徒は残しておく暗黙のサインかもしれません。
チャレンジスクールは不登校対応の高校から離陸を図っていませんか。不登校、あるいは引きこもり的な不登校生や登校がかなわない不登校経験者(!?)は、通信制高校およびサポート校に席を譲ると態度で示しつつあると思います。不登校生に進学先としてのチャレンジスクールは門戸が狭められつつあると言い換えられそうです。
その一方、チャレンジスクールの“人気”は高いままです。不登校経験者に加えて、不登校“親和”生徒がいるからです。私は、「引きこもりを社会参加させようとしていたのに、社会の方が引きこもりに近づいている」と書きましたが、それは中学生や高校生にもすでに現われているのです。この“親和”生徒とはそのような状態の子どもたちです。
ここから引き出されることは何でしょうか。チャレンジスクールに限らず多数の高校がチャレンジスクール模様になることが求められているということです。高校生年齢のかなり多くが不登校的ないしは不登校“親和”的になっているのです。それに対応することが求められているのです。
もちろん多数ある高校が同一色になる必要もないし、現実にそうはなりません。チャレンジスクール模様とはいえそれぞれの特色を持ちます。しかし全体として不登校生および不登校“親和”生徒を受け入れる状況が広まらないとうまく対応できない時代になっていることを示していると思えるのです。
学校は(この場合は高校ですが)不登校生の増大により、このような経路により対応してきたフリースクールの影響、そしてチャレンジスクールの経験を徐々に受け入れていくのです。それはこの時代の子どもたちの状態に(子どものほうではなく)学校のほうが適応しようとしている姿なのです。
しかし、大きな変化はまだ途上にあり、これからも社会の変化に沿った学校の変化は続いていくものと思います。
入学・就職試験に表わす別物の自分
先日は高校入学試験のための作文について書きました(2月18日「教育における『作文』」)。不登校体験者を受け入れるチャレンジスクールに入学するために「かつては不登校でしたが、いまは立ち直っています、大丈夫です」という内容の作文を求められ、またそれに“作戦”としてのる生徒の様子を知りました。
先日は、大学生が就職試験の臨むにあたっての履歴書を見せていただきました。大学時代の様子と、自分にできることを精一杯の“作戦”で現わし入社試験の合格をめざしているのです。
両方に通じることは、現実の自分と提出物に書いた自分がだんだん離れていくことです。学生の言葉によると、就職活動で失敗しないためです。その不安から現実の自分とは別物の自分を履歴書で表現しているのです。
受け取って読むほうは、たぶんそれが現実とは違う就職試験用のものであるとわかるでしょう。ですが(はなはな表現が悪いかもしれませんが)担当者としては弁解材料ができたのではないでしょうか。担当者は作文能力の試験をしているのではなく、必要な人材を募集しているです。多くの募集担当者にはその眼力があると期待しておきましょう。
このようは自分とは別物の自分を社会的背景の中で表現しなくてはならない事態が、特に若い世代の中である意味では組織的に広げられていることに気づかなくてはなりません。社会の虚構化が進んでいるといえるのです。
日本人は原子力発電の推進において“安全神話”がつくられていたこと、その虚構にびっくりしているはずなのです。ですがその傍らでは別の虚構が新たに生まれ、肥大化しているのです。少なくともその現場にいる人は気づいています。それがどれだけ大きな意味を持つのかはどうやら気づかないでいるように思えます。
先日、その一つの結果が内閣府(当初、総務省としたのは間違いです)から出されたようです。
それは項を改めてみることにします。
保健所の取り組みの情報集めから
先週から保健所として引きこもりにどのような取り組みをしているのかの情報提供のお願いを開始しました。情報提供用紙を作成し、FAXで送信しました(一部はFAX番号が不明。用紙の内容は3月16日付けで紹介)。
ある保健所(?)から「対応状態(引きこもりと周辺状態)」とは何を指すのかの質問を受けました。あわせて「いろいろな部門でいろいろな状態の人に対応しているので…」とも聞きました。
これを聞いて質問の意味がわかることがあり、「保健所として引きこもりへの対応を中心に書いてください」とお願いしたところおおよその見当がついたようです。
県によっては保健所が独立した部署になっていなくて、福祉部門の一部、あるいは健康福祉、高齢者対応などと合同のセクションになっているからです。
情報提供は30か所以上の保健所から期待しています。年度末(それとも新年度前)の時期で、保健所にとってこの時期がどういうものなのかはよくわかりません。もしかしたら多忙な時期なのかもしれません。こうして問い合わせをしていただけるのに感謝しています。
情報提供を受けたら、それらを詳細ページとしますが、詳細ページだけをまとめて見られるようにしたいと思います。Wikiシステムではそれも可能です。そうすれば保健所の引きこもり対応のおおよその状況が(個々の保健所の特色があるとしても)つかめるのではないかと思います。
杉並進路相談会の当日です
ただいま3月18日の午前8時です。
進路相談会の日です。空模様はくもり、雨が降るかもしれませんが、そう寒くはないです。
11時に会場のセシオン杉並に集まり会場づくりをすることになっています。
昨日、セシオネット親の会の場に主催者メンバーが集まり、状況を確認しました。
事前の準備はすべて終わりました。
参加校は10校、それに相談サービスが2機関、会場のセシオン杉並にある杉並区社会教育センターにも参加していただきます。新参加は東海大付属望星高校とキズキ共育塾です。これら13のところが教育相談、進路相談などに対応します。
インタビュー形式で体験を話していただく不登校経験者は3名です。カウンセラーの心理相談の予約はもう少しできると話していました。会場で閲覧でき、自由に持ち帰れる学校案内書は156校になりました。その他にも1、2部の数校分があります。
今回はごく簡単な受付用紙を作りました。お知らせがどのようになっているのかを把握するためです。広報はほとんど杉並社会教育センターに頼っている状況があります。ここを改善する手がかりを得ようとするためです。
セシオネット親の会の席では、今年の高校入学の途中状況が話されました。不登校生、中退生の高校進学にとっては好転しているとはいえない気がしました。入学後を含めて対人関係づくりの機会が低下しているようにも思います。これらの事情はもう少し確認してから様子をまとめてみるつもりです。
しかし、数年前と比較すればよくなってはいるといえるのかもしれません。それでも生徒一人ひとりのところでは楽観的なことは言っておれないのも事実です。
相談会は午後1時から始めます。
保健所の詳細ページを企画
全国各地の保健所では引きこもり等にどのように対応をしているのでしょうか。かなり熱心に取り組んでいるところと、ほとんど対応できないところまで保健所ごとに様子が違う印象を持っています。
様子がわかるようにしたいという以前から考えていたこの企画にようやく手をつけることができそうです。質問用紙をつくり、各保健所からお返事をいただき、サイト上に掲載することにしました。
質問用紙のうち、すでに「保健所」ページに紹介している名称や連絡先以外の部分をここに書いておきます。質問用紙は「保健所の引きこもりと周辺事情への対応について(情報提供のお願い)」としました。
対応地域(市区郡地域)、対応状態(引きこもりと周辺状態)、対応者(専門職)。
対応方法につき該当するものがあればお知らせください。
①相談またはカウンセリングをしている( )
②講座または学習会を開いている( )
③親の会(主に引きこもり家族を対象にする親の会)( )
④障害者の家族に引きこもり家族が加わっている( )
⑤若者の居場所がある(主に引きこもり経験者などの当事者の会)
⑥保健師等が自宅訪問をしている( )
⑦関係機関や団体との協力はありませんか( )
⑧その他の対応( )
引きこもり傾向の子どもがいるご家族に伝えたいこと。
質問用紙は3月中に送信し、4月から「保健所」ページに個別の保健所の詳細ページを作る形で掲載していきます。30か所以上の保健所からの回答を期待しているところです。
進路相談会で答える不登校経験者を募集
3月18日の「不登校・中退生のための進路相談会」の準備はだいたい整いました。
今回の相談会では不登校経験者数人にインタビューで体験を話してもらうことにしました。
インタビューに答えていただく時間は合計1時間あります。
3名がインタビューに答えていただくのですが、もう1、2名増えてもいいと思います。
不登校の経験者の方で、自分が出て答えようという人はいませんか?
そういう人がいましたら、連絡をお願いいたします。
会は1時からですが、11時30分から事前の打ち合わせをします。
会場はセシオン杉並3階集会室(杉並区梅里1-22-32、東京メトロ丸の内線「東高円寺」5分)。謝礼として3000円程度をお支払いします。
事前連絡は不登校情報センターの松田まで(TEL03-3654-0181、メールopen@futoko.co.jp)。
前日の3月17日(土)は、通常のセシオネット親の会を高田馬場で開いています。そのぶん連絡をつけにくいので申し出は早めにお願いします。
いじめに取り組む会への返事
川崎市で「青少年育成連合会」の理事長としていじめ防止に取り組んでいる横田正弘さんから、活動報告と協力の連絡が届きました。それへの返事をいたしました。
「横田正弘さん、お久しぶりです。
不登校情報センターの松田武己です。福田正俊さんと一緒にいじめ問題に取り組んでから20年が過ぎました。 いじめの件数はそれなりの波はありますが、ズーッと続いています。
川崎での篠原真矢君のケースはほとんど何も知らずに来ました。少年らしい正義感にあふれる勇気ある中学生です。社会として、大人として申し訳ない気持ちです。
子どもの問題は大人社会に問題があり、それが際立って表れてしまうように思います。
その意味では根本的には大人社会の問題を何とかしなくてはならないはずですが、個人としても、不登校情報センターという団体としてもそういうことにはほとんど力を発揮できないでいます。
同時に子どもたちのいじめには(大人社会の問題の反映だからといって後回しにはできず)特別に取り上げて対処しないと、とんでもないことになってしまいます。
有名人を含めて多くの人たちがいじめをなくそうと呼びかけていますが、そういうことだけでは子どもの気持ちを大きく動かすことにはならないのではないか。ある部分の子どもたちは私たちの思いのはるか先にいます。
私には置かれた条件の中でどういう取り組みをすればいいのかはよくわかりません。
いじめを受けている子の親からときどき電話相談があります。
いじめ後遺症ともいえる高齢者(なかには五十代になりなお社会に入れない人も)からも対処法はどうすればいいのか、などの相談が入ります。
それぞれに応じたことはお返事していますが、決定打にはなっていません。
いずれにしても事態が発生した後のことです。事態の進行中のことはその情報自体が届きません。横田さんのところでは進行形の事態が届くように思います。
そういうときの対処法、そういう事態の進行中の把握方法ももしかしたらご存知なのかもしれません。
想像ですが、私と横田さんの教育観は必ずしも近くはないかもしれません。しかし、子どものことがとりわけ好きで、子どもたちが未来の日本であることを信じて、最善の状態をつくりたいという思いは共通しているものと思わずにはいられません。
これからも何かご教示いただければさいわいです。
可能な協力はするつもりでいます。
2012年3月14日 松田武己」
〔福田正俊さんはペンネーム・三田大作で『いじめで子どもが死なないために』を出版し、私はその出版に協力しました〕。
不登校情報センターと進路相談会の案内
杉並の進路相談会の機会に2点の冊子をつくりました。
関心のある方には2点セットでお譲りします。送料込み100円(切手)。
(1)『NPO不登校情報センター』案内書(目次)
ホームページの概要、ひきこもり経験者による手紙相談、カフェ&スペースを案内します、一緒に編み物しませんか? わが子に訪問サポートを考えてみる会、『OYA・OYAネット』、有料お手伝い(ヘルプデスク、英文の翻訳、文書入力、将棋の出前サービス、カラーセラピーレッスン)・松田武己の面接相談、不定期刊『ひきコミ』、第5回片隅にいる私たちの想造展。
* 引きこもり経験者が得意なこと・できることを生かして“仕事づくり”をめざしています。それを列挙して紹介しました(太字の部分)。
(2)『第14回不登校・中退者のための進路相談会』冊子(参加校・団体の紹介)
アミータ福祉教育学院、和泉自由学校、親と子の相談室SORA、鹿島学園高等学校、学研のサポート校WILL、キズキ共育塾、晃陽学園高等学校東京校、東海大学付属望星高等学校、不登校情報センター、北星学園余市高等学校、代々木高等学校、わせがく高等学校東京キャンパス。
依頼・送料送り先=不登校情報センター(〒124-0024東京都葛飾区新小岩2-3-11-503)。 *「2点セットを希望」と書き、切手を同封し、送り先も忘れずに書いてください。