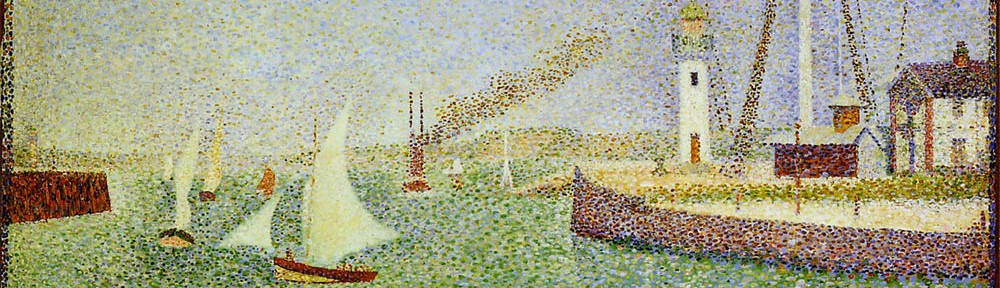5月3日のパネルディスカッションの席で、引きこもり経験者の居場所(スペース)の様子が話されました。
支援者と当事者との関係はできる(できる人が居場所に定着する)けれども、当事者の横の関係はできづらいという点が出ました。それが横の関係ならば、支援者(ここでは松田となります)と当事者の関係は縦の関係となります。
他の支援団体の様子を聞いても、この点はある程度は共通しています。
それどころか、横の関係においては友好的な関係ができないばかりか、ときには排除しあう関係や避けあっている関係も珍しくはありません。
組織的な人間関係づくりが苦手な人がほとんどですので、対抗するグループが敵対レベルになることはまずありません。排除しあっている人の親しい数人のなかに自分と親しくなれそうな人もいて、この関係は個人的な好悪感にとどまることがほとんどです。
さてこの縦横の居場所の人間関係に、この席では斜めの関係が指摘されました。
その役割を果たすのが、このスペース参加する研究者・学生(出席した堀口佐知子さんを指します)と何人かの母親です。
当事者はこの支援者を標榜しない研究者や母親の、あるときは何かを聞かれあるときは自分から話をもちかけていって、相応の話のできる関係ができていきます。
カウンセラーさんもいますが、直接にカウンセリングを受ける関係ではないカウンセラーさんがこのような役割になることもあります。
場合によっては当事者がそれに近い役割になることもあります。
もちろんこれには個人差があり、どの当事者も斜めの関係を利用するわけではありません。
この斜めの関係は十分に評価されていません。
もしかしたらそういう場面が他の居場所においてはあまりないのかもしれません。
不登校情報センターの居場所の歴史のなかではこの面が意外に大きかったと思います。
というのも私自身が支援者というよりも、それ以外の理解者として不登校・引きこもりに関わり始め、ここまで進んできたと思えるからです。