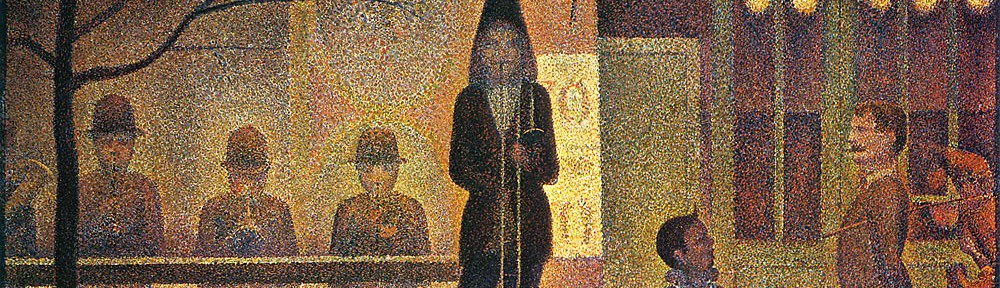引きこもりも30代以上になると、個人個人の状況に応じた対応が必要になります。このオーダーメイドの取り組みをざっと紹介します。
(1)病院に同行
同行した人は数人(十名未満)います。女性が多いですが男性もいます。治療室に一緒に入った人もいますし、本人診察後、医師から呼ばれて診療室に入ったこともあります。家族と一緒に医師に面会したこともあります。
予診のときに本人に代わって知り得る状況を話さざるを得ないこともありました。どこまでを話すべきかが難しいです。本人が話せない状態もあり、最低限のことを私が話さなくてはならずやむなく話しましたが、あとで「…あのことは話してほしくなかった」と言われたこともあります。
多くの医師の印象は意外と解放的です。医師ではなくカウンセラーの面接に同席したこともあります。
これらは医師と話すのが不安というより、病院に行く(特に初診時)のに本人の不安があり、それへの同行です。その結果、診察の現場等にも同席することになったのだと思います。
(2)一人暮らしのためのアパート探しに同行
例は多くありません。不動産会社に一緒に行った例、そこで社員と一緒にアパート等の部屋を一緒に見て回った例です。どちらでもなく一人暮らしをするのだと言って、転居先の候補を外から見て回った例もあります。本人は自分だけで判断するのに不安があり、そのための同行になったものと思います。男女両方がいます。
不動産会社の社員はごく普通の対応です。実際の大家さん(家主)に会うということはありません。これでいいのかどうかは別のことですが。
(3)生活保護のための社会福祉事務所に同行
きわめて切迫した状態で社会福祉事務所に一緒に行ったこともあります。NPO法人理事長という名刺が役立つことがあるとすればこのときです。
直接間接に生活保護の申請に関わったのは4名ですが、他に生活保護の受給条件を聞くために一緒に福祉事務所に行ったこともあります。これも男女両方います。
福祉事務所の職員は基本的に親切丁寧です。ときどき聞く“冷たい対応の職員”というのは、一人で福祉事務所に相談に行ったときに発生するのではないかと、うがった見方をしたくなります。
(4)職探しに同行
振り返るに私にはこの同行経験がありません。障害者手帳をもつ人について就労相談に行く予定があったのですが、直前にキャンセルになったのが惜しいと思いました。
(5)入学先・転校先の学校に同行
これは比較的若い人なので多くは家族と一緒に学校に行きます。その家族について学校に行き、担当者と話す場に同席したことがあります。家族も判断するのに意見を聞きたいのだと思います。
本人は入学できるかどうかを心配します。しかし、それはあまり問題ではなく、この学校はどういう雰囲気の学校なのかを観察する機会になります。
日別アーカイブ: 2015年5月2日
皮膚感覚・内臓感覚・脳神経系を学ぶ
最近読んだ本を少し紹介します。
(1)傳田光洋『皮膚感覚と人間のこころ』新潮社・新潮選書、2013年。生物の発生はその生物が一体であるためのまとまりを必要とします。その一体性を保持するものがやがて表皮になり、動物において皮膚になります。生物誕生の時から、表皮は生物がおかれた環境の中で感覚を形成し、適応するための工夫を積み重ねてきました。
それが人間という高等生物になって進化発展しました。それが人間の皮膚感覚にも受け継がれています。生物のもっとも原始的で基本的な感覚です。それがこころに結び付けられて身体科学・生物学としてポピュラーに紹介されている本です。
(2)福土審『内臓感覚 脳と腸との不思議な関係』日本放送出版協会・NHKBooks、2007年。生物の発生において表皮の次に生れたのは栄養補給のためのものです。
アメーバなどはそれを器官というには素人として自信はありませんが、進化した生物では消化器官になり、排泄器官が備わります。高等動物の場合は口、胃腸、肛門までの消化器系ができます。生物発生の初期からそれが生物の存在に影響する感覚器官の役割を持ちました。それが内臓感覚、「腹のムシ」という言葉の正体です。
人間の場合は腸の状態が脳の情動形成に直接的に影響します。この本は過敏性腸症候群(IBSといいます)の実際を見ながら身体科学として描かれる好著です。IBSは全人口の10~20%といいます。
(3)東大社会人科学講座 生命科学編『脳と心はどこまで科学でわかるか』南山堂、2009年。皮膚感覚、内臓感覚を超えて(ここで紹介する本の順番では)ようやく人の精神の本場ともいえる脳と神経系にたどり着きます。本書は7人の講義記録です。読みやすいですが人間の精神活動の基本を脳・神経系で説明することの限界(愚といいたい)をシャープに悟らせてくれます。
健康人を見る限りにおいては、人間の言行を脳の働きとするのでいいかもしれませんが、それは表面的なことにかぎられます。通用する世界をわきまえさせてくれます。
(4)もう一冊、池谷敏郎『心臓を使わない健康法』マガジンハウス、2014年。ハートが心を代表すると考えられるので、心臓・循環器系も見ておく必要はあると思います。この本はそこを見ようとする趣旨ではなく、日常生活の健康法を書いています。読みやすさはいちばんなので別の意味でお勧めします。
紹介したうちの3冊については、いずれノートを記載したいと思います。