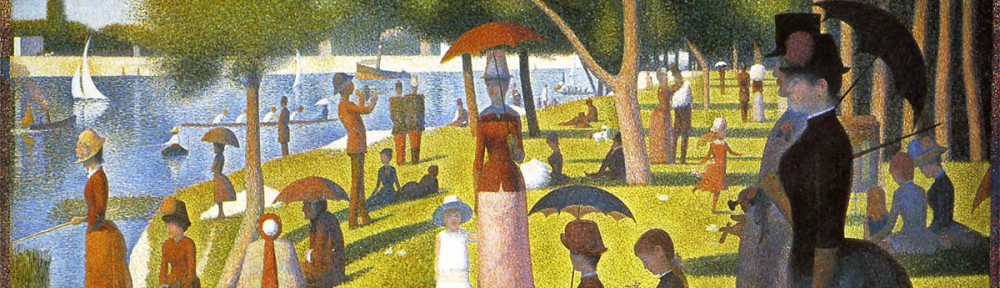不登校情報センターの親の会が始まったのは、2001年5月です。以後毎月欠かさずに開いていますので、累計170回以上になります。14年の間には大きな変化もあり、親の会の名称も2度変わりました。2012年5月からは「大人の引きこもりを考える教室」と称しています。それ以降の運営の基本形は同じですが、3年以上の期間のなかで少し変化もあります。最近数か月の様子を報告します。
定例会は毎月第2日曜日の午後1時~3時までの2時間です。
毎回の参加者数は10名から15名ぐらいが多いです。そのうち当事者(引きこもりの経験者)が数名参加するのが特色の1つです。
司会運営は私がします。会合の時間が2時間(30分くらい延長することもあります)、発言を希望しない親以外は全員から発言してもらいますので、1人当たり10~15分程度で近況を話してもらい対応方法を含む意見交換になります。
これを参加者が全員で聞きます。他の人の話しを聞きながら自分と子どもの場合を考えるのです。これらを聞くのに重点のある参加者もいます。
5人から10人が話しますので、短時間に収めるにはあまり脱線はしないような司会運営が必要になります。
かなり以前には数十人の親が参加した時期もありました。当時は状態の理解や感情面を共有することはできましたが、対応策を具体化する点が弱かったと思います。いまの内容を維持するには現状程度の参加者数がいいと思います。
参加する常連の親から聞くことは、子どもの様子がある程度わかるので、一通りの状況報告と意見交換は短時間で終わります。
初めて参加した人などは、状況報告や意見交換が長くなりやすいです。初参加者が多いと常連参加者の発言時間がとれないこともあります。
会の終了は3時過ぎなので(3時半を過ぎることはあまりありません)、その後、当事者を交えてのフリートークになります。隣り合わせの人や、当事者の誰かを囲んで話すなど、あちこちで会話が広がります。この時間帯は参加者の都合でいつ帰ってもいいわけです。それでも時には7時とか、8時過ぎまで続くこともあります。公式の親の会よりもこちらに関心・期待を持つ人もいると思います。かつての親の会にあった雰囲気がここにあり、しかも当事者が混じっている分いい形ができていると思います。
意見交流の内容面では、子どもが示すちょっとした動きや言葉をどう理解したらいいのか、親としてどう対応したらいいのか、外出の手掛かり、人とつながる手がかり…などをはじめいろいろな問題がでます。これらは参加している当事者からの体験したことを答えてもらうとわかりやすくなります。彼ら彼女らのことばは飾りがなく真情があふれているので納得しやすいのです。
時には年金の支払い、遺産相続、親族の関係などにもテーマが広がり…葬儀のし方を話したこともあります。これらも当事者の関心があり貴重な参考意見です。最近よく出るのは生活困窮者対策の福祉制度です。
そういう中でとりわけ関心が高いのは当事者がどうして引きこもりから抜け出したのか、動く気持ちになったかを聞くことです。アルバイトを始めた、派遣会社に登録した、仕事についた話にはよく耳を傾けています。当事者の体験談は断片的なことでも聞き逃さないみたいです。
当事者の話しで多いのは対人関係やコミュニケーション、職場での動き方などです。ここに表われる引きこもり経験者の話しは私にとっても貴重な情報源であり、引きこもりの心理やふるまいを理解する機会になります。
親の会の役割は親にとって有効であるばかりでなく、参加する当事者にとっても有効です。自分の体験したことを相対化する、出席者から質問されたことに答える形でことばにできるのです。そのことは自分が経験したことの理解を進めます。その意味では引きこもり経験者も親の会に参加するといいと思います。
親の会は引きこもりの理解、とりわけわが子との関係を改善するためのものです。私が意識するのはその理解を家族以外の他者とどう結びつけていくのかです。不登校情報センターには作業をする居場所ができています。ここにつなぐ方法が1つです。しかし簡単ではありません。この部分は「居場所ワーク」の項目で別に書きます。
その前に、家にいる引きこもる当事者と接触しなくてはなりません。自ら訪問を考えますが、無造作に訪ねても顔を合わせられません。そのための段取り、“作戦”が必要です。この部分は「訪問サポート」と「同行サポート」(5月2日「当事者に同行するオーダーメイドの取り組み」)の項目で別に書きます。
〔これは「かつしか子ども・若者応援ネットワーク」でまとめる報告書に提出する文書の下書きになります〕