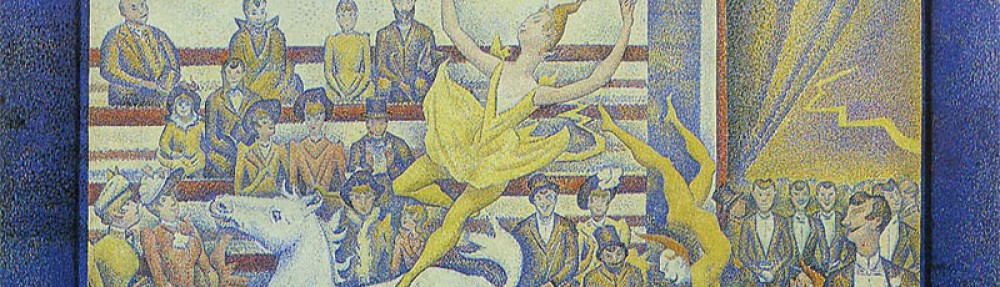4月号は、本田夏惟人くんの「大学生のときのひきこもりを卒業して」が最終回(第6回)になりました。連載は冊子にしました(B5版12ページ)。次は別のだれかの体験記がほしいところです。投稿を待っています。
松田武己は「「自傷他害」の事件になる前に対応が必要です」というある市長への手紙を書いたので、その要旨を掲載しました。
4月の予定では、9日(土)にパステルアート教室(13時)、ゲーム交流会:9日(16時)、セルフサービスカフェ:21日(木)15時。
不登校・ひきこもりの親の会は、23日(土)13時、それとは別にトカネット親の会も開きます。16日(土)13時。
大人のひきこもりを考える教室は、第2日曜日(4月10日)13時です。
Sさんが取り組む「ひきこもり大学in下町」は、5月の連休明けの5月8日(日)です。5月の大人のひきこもりを考える教室に重なるので、こちらに合流。場所は亀戸のカメリアホールになります。参加者を集めるのにSさんはあちこちに呼びかけに回っています。
月末・年度末になり、31日にはお花見を入れ時間の余裕がなくなったので、『ポラリス通信』4月号は4月に入ってから送ります。
月別アーカイブ: 2016年3月
上野公園で花見、再録
31日(木)は天候も桜の具合もよさそうです。
上野公園の花見には参加予定が10名を超えました。
考え中とか、微妙という人もちらほらいますので、も少し増えるかもしれません。
ウィークデイなのでそれほどには混雑はしないと思いますが…、持っていく敷物を確認しています。
◆上野駅公園口…13:00改札集合
◆当日緊急連絡先 090ー4953ー6033(藤原)
登校拒否・不登校問題研究会の結成に参加しました
全国登校拒否・不登校問題研究会の結成総会が開かれ参加しました(24日)。東京電機大学の前島康男さんの呼びかけです。
研究課題として12項目が揚げられました。研究方法は、文献研究(約40万点あるといいます)と調査研究などをあげています。私はたぶん実践からの研究になるでしょう。サイト制作のために学校、相談室、適応指導教室、フリースクール、親の会などの情報も継続的に入手できるのでそれらを生かすことができるかもしれません。
研究報告は『報告集』を適宜発行することになっています。
結成総会の場では、新潟大学の世取山洋介さんが「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の批判的検討」と題する報告を行いました。
虚弱気質、抜け殻、般若などを追加し300語句に
『ひきこもり国語辞典』という自作本をつくり販売しています。完成したのは2013年4月です。
その後もこの辞書に入れる語句を追加し、これはサイト内に掲載しています。
次の語句をまとめて追加しました。「溺れる、偽装、虚弱気質、角が生えてくる、とてもよかった、抜け殻、乗っ取られ感、ピン止め、要塞、流浪の民」。…
語句数が累計300を超えました。できれば市販本にしたいところです。
語句は情報センターに来ている人の会話などからピックアップしたものです。個人的な経験が言葉に出て、納得できたり、驚いたり…。1人だけの語句もありますし、複数の人の言葉から合成したものもあります。
これからも語句は追加しますので、心当たりのある方は自分なりの、引きこもりらしい(必ずしも引きこもり限定的ではありません)言行を表わす言葉を、エピソードとともに送ってください。
実際に辞書に載せるものは、松田武己の責任で表現します。
お名前や連絡先もお願いします。もし市販本になったら(?)稿料計算の材料にします。これまで40名以上からの語句を集め、いちばん多い人は20以上の語句を提供しています。
東京シューレ出版のページをつくりました
ときどき以前の相談者等から連絡をいただくことがあります。
先日もそんな連絡がありました。
その人が本を出版したと書いてあり、出版社発行の書籍案内が同封されていました。東京シューレ出版なので多少のなじみもあります。…
アマゾンの本を調べてみましたら、案内にあった本は全部取り扱い中であるとわかりました。そこでこの出版社のページをつくりました。
取り扱う本ぜんぶの出版社をつくろうというのではなく、特定の関連性の高い出版社に限定して広げてみようかと考えています。
個別プログラム方式と個別伴走型方式の違い
フリースクールやホームスクールを義務教育の一つの形態として位置付けることが見送られました。国会で議論されている多様な就学機会を確保する法案のなかのことです。
義務教育の場を学校に限定してきた教育の大転換になると注目されたのですが、「不登校を助長することになる」などの慎重論が上回ったためだといいます。
私は学校以外の教育を進めるのに2つの考え方があることが明瞭になったと理解しています。
1つは、生徒個人の状態を判断して、それに沿った個別プログラムを作成し、指導計画をつくり支援していくもの。これを個別プログラム方式と呼びましょう。今回の法案ではこの考え方が取り入れられていたようです。
もう一つは、そういう個別の指導計画は生徒を軌道に乗せて進もうとするもので、個人の提起する問題を置き去りにするという批判です。これを個別伴走型方式と呼びましょう。
実はひきこもりの支援に関しても同じことが生まれています。私の経験からすると個別プログラム方式はある時点から生徒・当事者の状態とは離れてしまいます。方式は絶えず修正しなくてはならないものです。個別プログラム方式はそれが意図されずに進み、当事者が置き去りにされてしまいやすいのです。
絶えず修正するとは、言葉を代えれば個別伴走型方式になることです。当事者の周囲にいて様子を見ながら対応策をつねに変えていくことになります。当事者の様子から離れることは少ないですが、難しい面もあります。当事者の様子に合わせて指導が漂流していることもあります。
福祉的な支援においては、当事者の関与を除いた解決策はないことが明確になっています。これを教育の場でも採用するしかないと思います。
目標を大きくし、当事者が向かう方向に手を加えず、伴走ないしは後ろから押していく形が望ましいと思うのです。支援現場では試行錯誤の連続ですが、私にはそういう姿も当事者にも見えてしまうのがいいと考えています。もともと完全はないからです。
寮のある高校を探す再入学希望の18歳
3月も後半になりました。
スロースターターの多い不登校生、中退生です。ようやく4月からの入学・再入学に動き始める人がいます。
この日は「親から離れて寮のある高校を探している」という、高1の途中で中退した18歳の女子です。
いろいろ聞いたのですが、情報センターに保管している寮のある高校の学校案内書をまとめて送ることにしました(7校分)。それらを見て考えていただいたうえで、何かあればまた連絡をしてもらうことにしました。
親から離れたい、高校だけは卒業しておきたい、というのが動機のようです。親もこれを認めているようです。
高校入学・再入学の動きは、5月の連休近くまで続きます。
1つの学校に2つの学校名がある
不登校情報センターのサイトをつくって10年以上が過ぎました。
そこで感じるややこしさの一つが、「1つの学校に2つの学校名がある」ことです。これは生徒が同時に2つの学校で学んでいる事態の発生にも対応しています。どちらかと言えば、生徒のダブルスクール化が先だったのですが、今ではどちらが先か後かはあまり関係がなくなっていると思います。
自体が発生するのは、通信制高校の連携制度です。法制的には技能連携施設というのがあり、これは通信制高校とともに定時制高校にもあります。
しかし、通信制高校でこれが広がりました。これを技能連携校、略称で技連校と呼ばれています。主に技術・資格を習得する専門学校系の高等専修学校が該当します。
それに加えて通信制高校にはサポート校が生まれました。1980年代の終わりに、不登校生や中退生の受け皿として広がったものです。サポート校になるのはいろいろですが、長らくその地域で学習塾などの活動をしてきたところが多くなってきました。
2つの学校名があるのは、技能連携校とサポート校です。技能連携校の方は元々知られてきた専修学校の名前をのこしながら、通信制高校の名前を付けていきます。学習塾などは「○○高等学校▽学習センター」みたいな名前になります。こちらの方の通りがいいので校名の力点をこちらに置いていく傾向があります。
生徒は、1つの学校に居ながらにして2つの学校に在籍することになります。
生徒第一と考えたいので私は容認すべきであると思いますが、ややこしいことは確かです。
元不登校の娘さんがラインスタンプを作成
不登校の親の会に来ているお母さんから娘さんがラインスタンプを作成して2組が販売中になっていると聞きました。40作品が1組です。
「yuyuyu」さんの名前で「カエルンルン」が出てきました。もう一つは「虫ちゃんたちの日常」です。さらに第3のシリーズも作成しているといいます。
不登校情報センターのサイト内の適当な場所からアクセスできるようにしようと思っています。…
不登校や引きこもりの経験者で同じようなことをしている人がいましたら連絡をください。ブログを書いている不登校・ひきこもりの当事者のも掲載し紹介しています。
「TheGamer」の数並べに勝てずちょっと残念
18日のゲーム交流会は、見学者として先日のかつしか区民大学の講座「子どもがピンチ!」分科会に参加したNkさんが来ました。その時のコーディネーター役の三田くんがこのゲームの主催です。
4、5名でいくつかのカードゲームをしました。戦略を考えながらやるものです。カードゲームに夢中になっている子どもがいますが、確かに集中させます。4時過ぎから7時近くまで3時間近くしていました。
「TheGamer」というとても特定のゲームを指すものとは思えない名前の、数字を並べるゲームは全員で挑戦するのですが、「いい結果は出せても勝利できない」ため、何度も繰り返してしまいました。ちょっと残念。
次回はパソコンゲームをつくっているオーストラリアの青年Gくんにも声をかけるため4月9日(土曜日4時ころから)を予定しました。Nkさんは就職活動中ですが、来れそうなら参加します。9日はあべさんのパステルアート教室があり、その後の時間です。