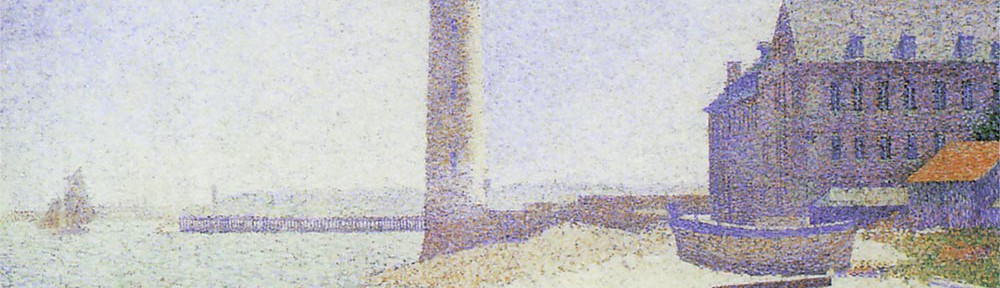ひきこもって家にいる人にとっては、「何時から学校に行くんだ」「そろそろ働きに行ってもいいころじゃないか」と親から追及されるのは嫌なものです。とくに自分でもそうしたいのにできないでいると思う人にはウザイのです。
家族と顔を合わせなければならない食事時になると、そういう言葉がいつ飛んでくるかわかりません。目を合わせないように急いで食べる、自分の部屋の持って行って食べるというのはその防衛策です。
親の方もひきこもっている子どもから何とか早く学校に行くとか、働きに行くという言葉がほしいのです。いつこの種の言葉が飛んできてもおかしくはない状況です。
これは精神衛生的にもいいことではありません。ここは“休戦協定”を提案してはどうでしょうか。
子ども側から提案するときは「(学校に行ける気持ちになるまで・働こうとなるまで)どうしたいか決めたら自分から話すので、それまでは待っていてほしい」と告げることです。
親から提案するときは「どうするかあなたの答えを待っている。それまでは注文を付けないからゆっくり食事をしなさい」というようなことがいいでしょう。
こう並べて見ると子どもからの提案は親から催促を受けやすいことがわかります。自分から言っといて後はなしのつぶて……と思われやすいのです。いい提案のしかた、話し方を工夫しなくてはなりません。
ともあれ親から提案するのが効果的です。これが“休戦協定”です。
ところが親からこの“休戦協定”は破られやすいのです。早く結論を出して動き出してほしいからです。そう簡単にいかない事情はわかっていても親はそうしがちです。
理由は親が不安になるからです。その不安を解消するために何かの答えを欲しいのです。親はしんぼうづよくないとつとまりません。
それに加えて、親として何もしないでいるのではないかと心配になります。周囲の人からそうは思われたくないがために「しょっちゅう言ってはいるのですけれどね」というアリバイづくりをする人もいます。要するに親の不安解消や周りから言われたときに何もしていないのじゃないという言い訳づくりのためにひきこもる子どもを追求し、何らかの反応を得ようとするのです。これは子どものためではなく、親のためのことばです。
“休戦協定”を提案し、時間をかけてゆっくりとことを進めます。数か月してから「あれはどうなった」ときく、数回繰り返したら「期限を決めてあなたの考えを聞かせて…」という具合です。その先に親側からの「ひきこもる子どもにできそうな提案」が考えられます。その提案にはいくつかの方法がありますが、子どもの状態によります。比較的多いのは、外から誰かに来てもらう方法です。この提案は(個人差はありますが)子どもが自分で考え、迷い模索し、提案を受けとめ、心のうちで咀嚼する時間が必要なのです。(つづく)
5月28日の不登校セミナ-のなかで感じたことを書きました。終りの方は要点だけなので詳しく書く必要がありそうです。