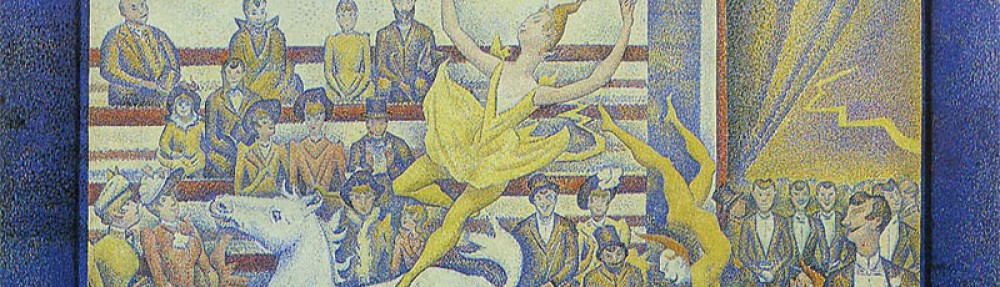眼鏡屋さんの前を通ると「色覚補正めがね」と書かれた大きなポスターが貼られています。はて、視力矯正でなく色覚補正とは、色弱用のメガネなのか? ポスターに近づいて確認しました。どうもそのようです。
小学校のころ検査を受けた色覚検査の表を思い出しました。あれに似たものがポスターにも色刷りされています。学校の時のものはもっと明瞭だった記憶がありますが、ポスターは色の輪郭がぼやけています。あえてそうしているのでしょう。
他の子に読めて自分だけ読めない字があった。他の子は読めず自分だけがその文字を読めた。色覚検査の用紙はそれを鮮やかに示していました。
私が色弱とわかったのは小学校のこの検査の時です。2年生ではなかったかと思います。そのときはちょっと特別扱いされた記憶があります。
そのときの検査用紙(のちに石井式と知りました)は、鮮やかすぎて(現実よりも極端?)、ポスターの色覚検査の表はぼやけて見えるようにしてあるのでしょうか(?)
ちょっと驚きだったのは、色覚をメガネで補正できるという点です。色彩感覚が働いていれば(色彩感覚がない場合はできない?)、それを補正できるところです。
聴覚などで使う補聴器もそれと同じ原理でしょうか。聴覚の場合は音を拡大する(強度をます)ことでしょう。色覚の場合は、拡大ではなく色の質を変換する必要があります。それが「色覚補正」の技術的な難関でこれまで世に出なかった背景理由の1つかもしれません。たぶん生活上の困難が聴覚ほどではなかったこともあるのでしょう。
その技術的な難関をメガネで行うのがすごいと思いました。どんな仕掛けのメガネなのか時間があれば眼鏡屋さんに聞こうと考えています。感覚器官を操作するのは難しいと思いますが、その外側でなら補正できる、それを確認しました。(医療技術は感覚器官にも手が付けられるレベルになりそうです)
引きこもり居場所だより
不登校情報センターのワークスペース、居場所、相談、親の会、ミニイベントなどの様子をお知らせいたします。2014年1月、不登校情報センター・センター便りの名称変更です。