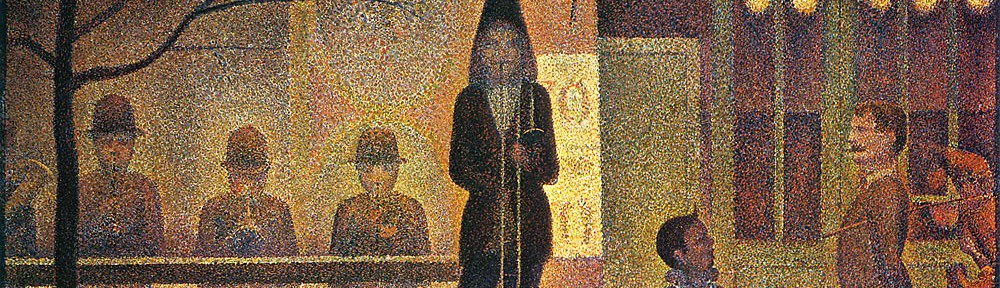昨年秋、15歳から39歳までのひきこもり数が54万人と内閣府から発表されました。
これは2015年12月に無作為に5000人を調査し、内閣府の基準でひきこもりと判断した回答者1.57%から全体を推計した数値です。
その後、各地でひきこもりの実態調査が行われ、40歳以上のひきこもりの人が全体の30%以上を占めるという報告が続きました。
厚生労働省のひきこもり定義もありますが、個人をひきこもりと確定するものではないので、推測値にとどまります。
実態を調べようがない壁に突き当たり、ひきこもりはどれくらいいるのかの数値がはっきりしません。
行政部門のひきこもり対応が進まないのはこの数値がはっきりしないことが要因の一つと考えられます。
ここで私は2つの提案を考えます。
①、1つは2020年に実施される国勢調査の機会を活用することです。
調査にひきこもりを近似的に把握する項目を設定することです。
職業を書き込む欄があります。
そこに無職、と回答した方に無職の期間がどれくらい続いているのかを書く欄を作ることです。
無職イコールひきこもり(またはニート)とは言えません。
障害で働けない人、高齢による人などもいます。さらに勤務先はなく創作活動をしている人もいますが、その全部が作家とか画家と答えるとも思えません。
それらとの区別は残ると思いますが、厚労省の推測値よりも実態に近くなると考えます。
2020年実施になる国勢調査のための有識者会議が設置され委員も決まっています。
それらを考えて、国勢調査を行う総務省に提案を送るつもりです。
②、提案はもう1つあります。厚生労働省のひきこもり定義はありますが、それを判断する人は決められていません。
医師はひきこもり状態の人を診て「精神障害があるかどうか」を診断しますが、一般にひきこもりの診断はしません。
そのため行政部門の数値はひきこもりの数値がぼやけるのです。
ひきこもりの判断とは、医学的な診断ではなく社会的状態像の判断です。
参考になるのは不登校の判断のしかたです。これは文科省の基準により学校長が行います。
状態像の判断は、基準を設けて判断できる人を決めていくのがいいと思います。
ひきこもりの判断は、厚生労働省のひきこもり定義に基づき、ひきこもりと周辺状態の人に対応をしている、団体機関にしてはどうでしょうか。
その団体機関で一定期間の実務経験をもち、当該対象者と接点・接触が持てる人です。
たとえば保健所の保健師・精神保健福祉士、心理相談室のカウンセラー、福祉機関の職員、民生委員などです。
特に公共機関の実務経験のある職員は、ある程度の期間に数回の接触の機会を持ったあと判断してもらうのがいいと考えます。
相談現場の実感としてひきこもりの人は公共機関との接触や面談的な受け答えをしやすいと考えられるからです(絶対的ではありませんが)。
これにより市区町村単位での該当者の存在がかなり明確になると思います。
行政としてひきこもりへの対応を進める基礎が整うでしょう。
引きこもり居場所だより
不登校情報センターのワークスペース、居場所、相談、親の会、ミニイベントなどの様子をお知らせいたします。2014年1月、不登校情報センター・センター便りの名称変更です。