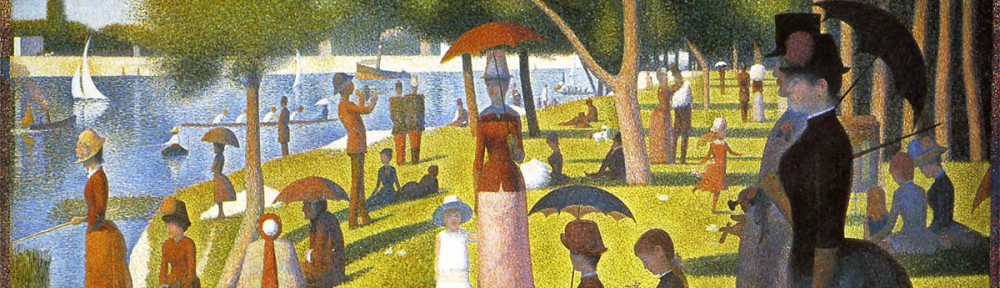これからフューチャーセッション庵に参加します(8月5日)。
予定した「自治体のおけるひきこもり対策の試案」を大幅に書き変えました。
その事情を、試案のまえがきに書きましたので紹介します。
これに参考にしたエンジさんの取り組みを書いたものと合わせて8ページの冊子にし持参します。
〔試案〕ミドルエイジ人材養成センター まえがき
8月1日発行の会報に「江戸川区ひきこもり社会参加企画(松田試案)」を載せました。
自治体でのひきこもり対応にどんな方法があるのか。より効果的な対応策の素案です。
2015年4月に生活困窮者自立支援法が施行されて、公式に基礎自治体(区市町村)がひきこもりにも取り組むようになりました。
それから3年ほどですが、納得できる施策はありません。
それ以前は都道府県と政令市が設置する精神保健福祉センター(その1セクションであるひきこもり支援センター)が管轄していました。
相談が中心で医学・心理的な対応と判断しています。
他方ではひきこもりの家族や当事者を中心に取り組んできた経験の蓄積があります。
その中でもとりわけ優れている方法をもってしても、それが広がらない、効果が十分でない、という印象をうけます。
難しいテーマであり、人や金があれば容易に解決できるテーマではないのです。
しかし、自治体が関与する新たなステージができました。発展させるにはどうしたらいいのか。
来年には全国的な統一地方選挙があります。
そこに向けていろいろな働きかけをするつもりで、何を訴えていくべきかをまとめた試案です。
そんな思いからでしたが、この試案もまだ不十分と思い、就業経験のないDくんに読んでもらい話しを聞かせてもらいました。主な感想は、就職はきついし、区役所が出てくると重くなる。居場所的なソフトな雰囲気にしたいと言いました。
Dくん的には居場所という言葉でもすでに自分の気持ちとは段差を感じる人がいるだろうといいます。
そういう言葉を使わない対応策があるのか?
頭の中をかき回していると、ふと半年前に相談に行った江戸川区シルバー人材センターが浮かびました。
短時間就労をすすめる準公的機関ともいうべきシルバー人材センターならどうだろうか。
働くとしても就職でなく、区役所ほどの役所感もなく、それなりに安心・安定感がある。
ひきこもりなる言葉もありません。ここはそれを援用してミドルエイジ人材養成センターです。
これまで関わった多くのひきこもり経験者の状態を思い、不登校情報センターが到達した「ひきこもりを仕事につけるリクルート活動」(資料参照)を結び付ける。
その結び付け役がミドルエイジ人材養成センターとすればではどうなるか。
このフレームの中で試案を全部書き直しました。依然として試案です。
全国の自治体を対象にしたいのですが、まずは在住の東京都江戸川区を想定します。
地域の事情はそれぞれで、それらの多くを織り込めませんが、1つの雛形にして、研究会をつくりほかの地域にも広げられれば…。
http://www.futoko.info/zzmediawiki/ひきこもりを仕事につけるリクルート活動