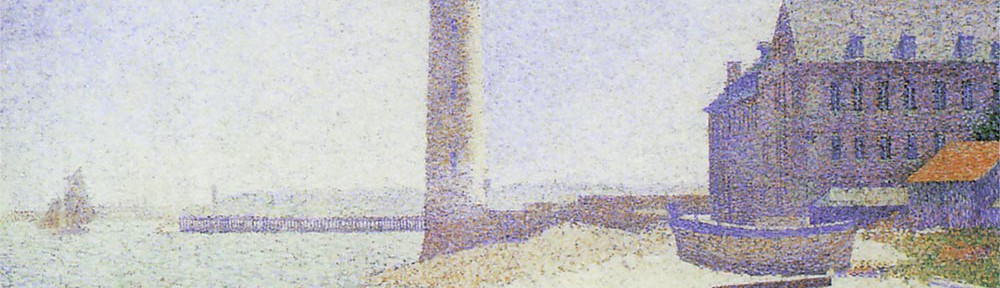子育ては、家族内ケアの中心部分です。今日では保育園・幼稚園が広がり、乳児からの受入れるところもあります。小学生以降の学齢期は主要には学校であり、明治期の設立以降これは全国に設立されました。
これらが家庭外にある子育て施設です。それらに加えて今日、学校と並ぶもう1つの家庭外の、学校以外の子育て施設が生まれつつある時代に入ったと私には思えます。
以前からあるのは学童保育ではないでしょうか。あるいは学習塾や習い事教室なども相当するでしょう。これらの需要が増えたのは、子どもを持つ主婦の就業機会が増えてきたことが背景にあります。
最近十年には、これらに加えて子ども食堂の全国的増加、2017年施行の教育機会確保法以降(コロナ禍を経験して)には不登校の小中学生の増大も関わっています。いま全国各地の自治体は、子どもの居場所づくりに積極的に取り組まざるをえなくなっています。
教師の働き方改革にあわせて、学校の部活動を地域のスポーツクラブなどに移行させる動きもあり、文化部的活動もこれに匹敵する動きがあると予想できます。これらは「校内フリースクール」設立の動きとあいまって、学校制度が大きく変わっていく過程が始まったものと想定できます。家庭・家族制度の変動はより長期を要するでしょうが、学校をめぐる変化は、それよりは短期間に進むと考えられます。
小学校以前を含めて小学生から高校年齢までの子育ては、家庭外の各種の受け入れ手段・施設が求められる時代に入っていると判断できます。こうして子育てに関わる家事労働の評価は、乳幼児期から学齢期まで対象となる家庭外サービス業・施設ができています。あわせてボランティア活動を評価する比較対象とされる要素が生まれていると考えることも可能になっているのです。
引きこもり居場所だより
不登校情報センターのワークスペース、居場所、相談、親の会、ミニイベントなどの様子をお知らせいたします。2014年1月、不登校情報センター・センター便りの名称変更です。