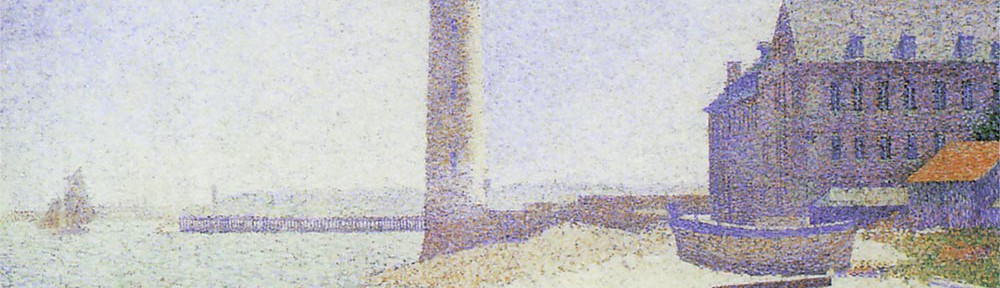不登校情報センターの設立は1995年です。教育誌を編集していた時期から不登校の相談を受け、相談先情報を広げる目的で不登校情報センターをつくったのです。ところが実際には不登校情報センターへの相談が増えていきました。
その時期(90年代後半)の相談は十代後半から20代前半の年齢が多く、相談に来るのは主に親でした。様子は少しずつ違いますし、当時と似た状態の人はいまもいます。年齢は十代後半から20代前半で、相談内容も90年代後半とだいたい同じです。
私は現在の「社会的ひきこもり」は全体として日本社会がゆたかになったためと考えますが、他方には「ゆたかさ」とは言えない生活状態におかれ、ひきこもりになる人もいるわけです。
本書『アルバイト体験記/対人恐怖との葛藤』の著者、高村ぴのさんは90年代後半から不登校やひきこもり状態に近い精神状態におかれたものです。
医師の診断を受ければ、対人恐怖症、神経症または強迫神経症さらには不安神経症とか社会不安症…という系列の診断を受けることでしょう。遠因にはいじめを受けた体験を忘れるわけにはいきませんが、生まれつきの感受性の強さも関係していると思います。
症状の程度によっては、心身状況を悪化させてしまいます。医師に相談すると多くは就業を勧められないでしょう。そういう状態にありながら、経済生活上の切迫した環境のなかで、彼女は15歳でアルバイトに就く道を選びました。彼女はさいわい「妥協する」道を経験し、対人関係がわずかずつ改善している様子が読み取れます。
私(松田)の知る限りでもこれに似た事情のなかで働く道に進んだ人はいます。何人かはこの難関を通り抜けました。案外すんなり抜けた人もいるようですが、そう容易な道ではない人もまたいます。高村さんの手記はそういうばあいどのような苦難を通らなければならないのかを体験談として表現してくれました。
私は、このような状態においては「生活保護を含む福祉の利用」を考え、制度の充実性を訴えます。しかし彼ら彼女らのなかにはそれを望まない、拒絶する人もいます。その生活状態のなかで葛藤するすさまじい努力を応援するしかありません。その私の気持ちをどう表わせばいいのか迷いますが、自分の高校時代に経験した貧乏生活がある種の心の居所となっていると思うこともあります(心理面は違うかもしれません)。そしてハラハラしながら見守る気持ちになってしまいます。
「アルバイト体験記」は、15歳の中学卒で働き始めた人の実話です。その試練をリアルに語ってくれました。文中に一人の老人の姿が彼女を勇気づけています。そこまでではないにしても、周囲の人には目に見える応援ではなくても、「フラットに、普通に」目を向けてほしいと思うのです。
このような生活や環境条件から「働くに働けない」状態でいながら働かざるを得ない人はいまもいます。30代、40代、50代で、ひきこもり状態がつづいてきたなかでそうするしかない(と思う)人たちです。
うまくすり抜ける(?)方法はあるかもしれませんが、それは手助けする人との協力が前提であり、この条件がないなかでは期待できないのです。そして正面からこの難しい事態に立ち向かい取り組んでいる人たち——それがどんな目にあっているのかを、間接的な文章表現でしか伝えられませんが、読んでいただくように期待します。