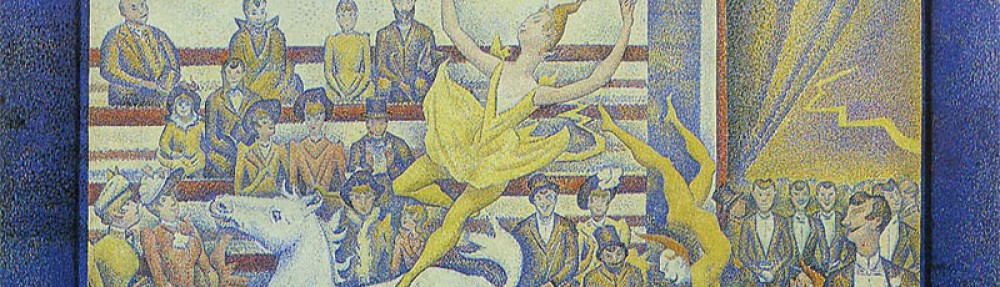社会的ひきこもりの起源 5-2
女性の社会進出に関する様子を石井寛治・編『近代日本流通史』(東京堂出版,2005)にみましょう。
働く女性が結婚し、家庭を築くにつれて家族の変化、社会の変化が生まれてきました。
『近代日本流通史』ではこれらの事情を次のように描いています。
「80年代後半は女性配偶者収入の増加が家計収入の増加に寄与した時期でもあった。
女性の社会進出はそれまでシャドウワークとして内部化されていた家事労働を外部化させる傾向を有する」(P200)。
「団塊(だんかい)ジュニアと言われる世代の低年齢化した激しい受験戦争やその反面での校内暴力や不登校などがその背景にあった。
外食費の増大は女性の社会進出が進む一方で、家事労働が依然として女性のみに押し付けられている現状を反映したものと思われる。
これは外食や「中食」と呼ばれる調理済み食品による家事労働の代替費用と考えることができる。
こうした支出の拡大はファストフードやファミリーレストランなどの業態を飛躍的に拡大させることとなった」(P203)
「こうした中流意識の拡大は、人々のライフスタイルを変化させ、その消費スタイルを変化させた。
そのなかでも、この時期に現れた注目すべき変化は家計の個別化現象であると思われる。
それまで家計は、世帯主収入に基本的に依存して営まれていた。
しかし、女性のフルタイムやパートタイムでの就労の拡大は彼女らに固有の所得を発生させ、これが女性の購買行動に変化を与えた。
就職により所得を得た子供も個別の家計を形成し、固有の生活スタイルを形成した。
さらに、核家族化が進展した結果として高齢者世帯の比率も高まっている。
このような家計の個別化・分散化は、消費行動の分散化現象を拡大するものであった。
女子就労率の上昇は、まとめ買いや調理済み・半調理済み食品の需要を高める。
モータリゼーションが進展した一方で、まとめ買いが拡大すれば多少遠距離でも低価格で品揃えの豊富な大規模店舗が集客力を高めることは当然であった。
駐車場のある郊外立地の大規模スーパーがこの時期に急拡大した理由である。
この時期に様々な業態の外食産業が発展したのも同じ理由からであった」(P204-205)
女性の社会進出(就業化)が家計に変化を与え、生活スタイルも変えたというのです。
それは家族関係を変えましたし、国民全体の生活スタイルも変えたのです。
家計はこれまでも一元管理とは言えなかったのですが、様子はかなり変わりました。
親子とも以前の家計に比べるなら個別の家計と固有の生活文化を広げました。
著者はこれを「家計の個別化・分散化」としています。
これらが1980年代後半以降の変化と考えられます。
しかし、核家族において主婦が働き始めるわけですから、さらに多くの役割が主婦に覆いかぶさりました。
それは家族内における子育ての面での対応力の低下につながり、著者が指摘する子どもの校内暴力や不登校にもつながります。
それだけではなく、全体では小部分と信じますが、家庭内暴力(DV)と子ども・高齢者への虐待の増大につながってきたと説明できます。
家庭内のこうした変化に伴うトラブルも生まれます。
離婚の増大はそれを解決する一つの方法でありますが、女性の人間的な対等関係の意識が向上している事情にもよります。
いろいろな生まれている変化の全部を女性の社会進出、働く女性が結婚し家庭を築いたことで説明しているのではありません。
女性が強くなった1つは、女性が就業により収入を得ることが関係すると考えられるのです。
しかし、社会全体の平等意識、憲法の保障する個人の権利が深く国民に定着してきている背景も見逃せません。
社会的な条件には、非正規雇用が増大し、雇用条件のセーフティネットが弱まり、国民のなかでの経済格差が大きくなっています。
離婚したシングルマザーに困窮が強まっている事態はそれを象徴するものでしょう。
現在の核家族を中心とする家族制度はこれらの問題を含んでいるわけです。
その他の事情を含めて新しい家族関係が求められ模索しながら徐々に進んでいると推測できます。