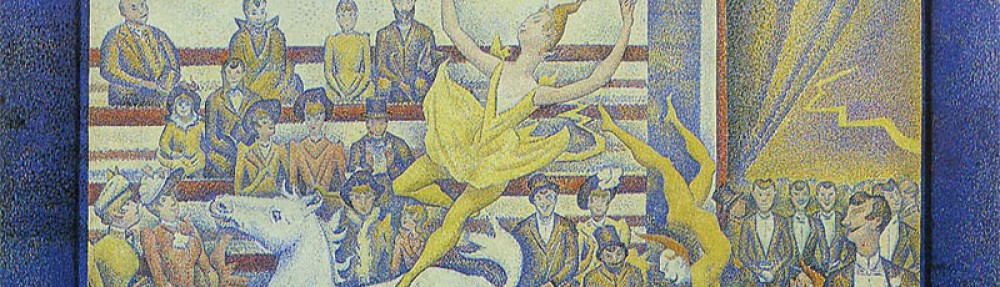シリーズ「なでしこ会講演その後7」(最終回)は、居場所で何をするのかは当事者がやることを応援すると話しました。感想としては次のようなものが寄せられています。
《居場所の役割の中に、当事者がやりたいことを見つける場、又それを応援する場、というお話しが、これからの居場所が目指すところと思います。》
《居場所からの発展する可能性を感じて嬉しくなりました。》
《居場所のある意味、方向性が分かりました。年齢も高齢化しつつ有るので、自分で好きな事から就労につなげていけると。》
《居場所は支援者が何をするのかを決めるのではなく、出来る事を応援すること。》
初めからそうであったとは言いがたいし、到達状況は十分ともいえません。その点を少し。
当事者が集まるようになって2、3年したころに私がしている本の編集業務を手伝うという人が現れました。ついで2000年5、6月に文通誌『ひきコミ』を発行することになりこの編集作業をする人が生まれました。いずれも私の仕事である編集業務が関係します。
そのうちに30歳前後の会の人が「不登校情報センターを働ける場所にしてください」といってきたわけです。あゆみ仕事企画を名乗りいくつかの試みをしました。内職はすぐに断念し、ポスティングは4年ほど続きましたが参加者が減ってこれも停止しました。DMの発送作業はいまもときどきあります。
それらのなかで成長したのがホームページづくりです。このホームページづくりも私が仕事にしていた学校や支援団体の情報提供です。出版物からインターネットに転換した時代的な背景があります。運もよかったと思います。
居場所で何をするのかは当事者がやることを応援するというのが当てはまるのは、むしろ最近のことです。
しかし、振り返ると当事者が自分の思い付きを試行できる環境があると感じたのでしょう。
① 必ずしもうまくいかなかったとはいえ、あゆみ仕事企画の取り組みがあります。
② そしてホームページづくりです。これは当事者から自発的に出たかどうかは微妙なところです。不登校情報センターの内容を発表するホームページづくりは何人かが試みました。そこに私のほうから学校や支援団体の情報を提供するサイト制作を呼びかけました。サイト制作を呼びかける私はその方面の知識は何もありませんから、それができる当事者に任せるしかありません。
③ パソコンを教えようと個人でパソコン教室を開いた人がいます。整体師を目指す人が呼びかけたところ、数人が“実験台”になりました。
こういう経験のなかで、当事者が自分のほうから何かをしたいと始めたのです。
これは仕事や作業に関してだけではなく、日常的に楽器、パソコン、スポーツ用具など当事者が持ち込める状態にあることに関係します。居場所は当事者が何かをしようとするときにそれを始めてもいい雰囲気にしたいところです。
2011年の夏に「引きこもり後を考える会」をしたいという人が現れました。このメンバーによる「引きこもりから抜けだす仕事づくり」集会を2011年10月に開きました。しかし、これはその集会を山場に消滅しました。
続いて仕事づくりをめざす人がそれぞれ何かを始めています。これらのなかで彼ら彼女らの仕事づくりに対個人サービス的なことが多いと気づいたのです。それは当事者にカウンセラー指向や個人授業的な教え役を望む人が多いという以前から言われ感じていたことと共通します。個人ブログを立ち上げ運営する人も生まれました。だから対個人サービス業に限定しなくてもいいのです。しかしこの仕事づくりの取り組みや実現の程度はまだ端緒的なものです。