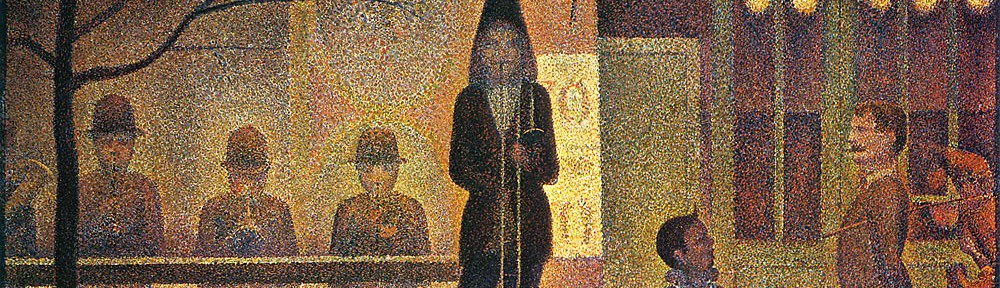私の経験的・実際的なモノの考え方の二番目は「目線を低くする」です。考え方としてはいいはずですが、私にとって大事なことで成功しているかどうか、判断が難いこともあります。
「民主主義とは多数決」はいくらか当たっていますが、いつもそうとは言えません。多数が賛成しある一人を責め、もしそれがいじめなら集団いじめを合理化することになります。
民主主義とはある集団グループの弱い立場にある人の利益が守られるのが、私の考え方です。選挙で多数に支持を得た人が当選するのは、選挙権をもつ人が平等であるという前提に立っており、その前提がおおむね保障されているから、選挙で多数の支持を得た人は当選し、民主的選挙といえるのです。
しかし、集団グループが相対的に小さいと特別に配慮を必要とする人はいます。ある地域とか企業・団体とか学級や家族では、弱い立場にいる人はいます。そういう人が不利益にならないようにするのがより進んだ民主主義です。
これを実現する方法が「目線を低くしてモノを見、考え、判断する」姿勢です。特定の集団やグループ内で、最も弱い立場にある人が不利益にならないようにしながら、多数の意志が実現できるようにすること、その方法の基本が「目線を低くする」ことになります。
しかし、私の実際にしてきたことは、(そう思っていたのですが)必ずしも成功したとは言えないかもしれません。取り組んできた中心のひきこもりの集まる居場所、その運営者としての自分の経験を挙げてみます。
居場所に集まってきた人のなかでも(全員全てに目が届いていたわけではありませんが)、状態の重い人の方に、私は気づく限りにおいて目を向けてきたと思います。症状が表に出る、その人の置かれた環境がひどいという人に私の関心が向いたのは「目線を低くした」1つの結果です。
この選択は自分でもある程度は肯定的に納得しています。私はひきこもり経験者の身心の状態、日常生活がどういう事態にあるのか、そこから理解し対応しようとしてきたと思います。
しかしその結果として、ひきこもりへの関わり方に成功していたともいえないと判断しています。それはひきこもりからの社会参加を促すための制度設定に向かう方面に前進してこなかったからです。それは対人関係づくりのプログラム、技術・知識を獲得する訓練に向かうのがよかったのかもしれません。例えば若者サポートステーションの設立です。各地にはそのように展開したところがあります。
不登校情報センターがそうならなかったのには、特別の理由があります。
それは別項目にして述べましょう。⇒ http://www.futoko.info/zzmediawiki/ 居場所での作業は収入を分配
若者サポートステーションの運営に向かった所が「目線を低くしてはこなかった」と言いたいのではなく、私のばあいはそう進まなかったのです。「目線を低くする」というだけでは欠けるものがあったのかもしれません。「目線を低くする」とは、その人の主に非社会的な面(症状や性格や生活条件など)に目が向き、ひきこもり全体の社会的な面への対応が後回しになった、と思えるからです。
それでも「目線を低くする」は私にとっては欠かせないスタンスであり、私の考え方の一つの構成部分です。
月別アーカイブ: 2024年6月
数値ではなく生身の人間を感じるのが大事
私のものの考え方・捉え方には原理的な面と経験的・実感的な面があります。
原理的な面は認識論とか論理学とでも表わしたらいいもので、比較的若い時期に学んだことがベースになっています。経験的・実感的な面は生きて生活するなかで知らず知らずのうちに身についたものです。原理的な認識論とは相反するものではありません。少なくとも自分の中ではそうです。
経験的・実感的な面には2つあると思います。今回はそのうち自分で経験してみる、人については抽象的な数字であっても「生身の人間を感じる」点について書きます。
月刊教育誌『子どもと教育』編集長をしていた1984年ごろです。年に1回か2回、通常号とは別に臨時増刊号として特別の特集号を企画・編集していました。例えば「いじめ」「学級づくり」がテーマです。
日本体育大学の正木健雄先生の研究室が毎年、子どものからだの調査をしており、正木先生の協力を得て「子どものからだ」の臨時増刊号を編集発行することになりました。手元にその号がなく、内容詳細は書けませんが、文部省もすすめる各地の子どものからだ調査を、各校でどのように取り組んでいるのかの教育実践記録と調査のまとめを、グラフにした内容でした。
臨時増刊号を発行した後、日本体育大学の正木研究室で検討会が開かれました。十人以上の研究者が中心に特徴や感想などを発表しました。その途中で突然、正木先生から「編集者として感想はどうですか?」的な指名がありました。
全く予期していなくて面くらったのですが、「私は調査結果を見ているけれども、現実の子どもを見ていません」とその場では特に発言しませんでした。その場かぎりの、根拠の乏しい、数字に頼るいいかげんな発表はすべきではないと強く思ったのです。
この経験は私には深い記憶に残りました。出版社を去り、ひきこもり経験者に囲まれる生活になったとき、私は生身の人に囲まれた生活においてようやく、身体状態を表わすいろいろな数値も意味をもつものだと実感しました。
同時に私は、一人ひとりの状態を、〈正式の面談〉場面だけではなく、できるだけ日常生活場面で見ることの意味や役割が欠かせないと自覚しました。さらにいつの間にか私は、「経験主義者」を自認するようになりました。外から見るだけではなく、自分なりに関わり経験する必要があると考えたのです。
ニュースなどで見聞きすることで、世の中の動きを知るのですが、それらをできるだけ自分の経験したことと照らし合わせて考える必要があるようになりました。それを文章に記録するときには、何らかの自分の経験を織り込んで書くように心がけています。それに適した経験的な実例がいつも都合よく思い出せるとは限りませんが…。
たぶんAI(人工知能)の活用が進んでも、その自分が経験した部分の記述はAI記述が広まってもほとんど書き込めない気がしています。
島根県知事の少子化対策・移住促進策
島根県の丸山達也知事が、少子化対策と移住政策を語っているのを見ました。2024年5~6月のネット上のABEMA Primeです。
この2つのテーマのうち少子化対策は全国的課題ですが、移住政策は特に人口減の著しい地域の課題(島根県も含む)で、しかも連動しています。
移住政策は、人口減がすすみ、地域の衰退が危惧される地域ではあの手この手の施策が市町村や県単位で執られています。6月に入って地方創成会議(増田寛也会長)が、2040年には全国700以上の市町村が消滅の危機にあると発表し注目されました。島根県は2016年発表で全19市町村のうち消滅可能性自治体は16市町村あるとされていました。今回は16市町村のうち12市町村が消滅可能性から脱却し4自治体が消滅可能性になると報告されています。島根県は少子化対策で前進をしていることになります(県全体の人口減少は続いています)。
丸山知事によると医療費の自治体支援が中学から高校生までに広がり(医療費無料の自治体も増加)、学校給食費の無料化が進んでいます。島根県全体の「少子化対策」とは、①結婚・出産に関しては縁結びボランティア(出雲大社にちなんだ取り組み)、コンピュータマッチング、不妊治療助成、産前産後ケアがあります。②子育ては子育て応援パスポート、子どもの医療費助成、保育料軽減、放課後学童クラブ支援などを挙げています。
不登校情報センターのサイトで紹介している「山村留学類」には、県外からの高校留学を導入する「しまね留学」も紹介しています。私の出身校である県立大田高校も、同じ市内で姉兄が進学した県立邇摩(にま)高校もこの「しまね留学実施校」になっています。また隠岐島では漁業就業支援も行われています。
島根県の女性出生率は1.62(全国4位、全国平均1.20、東京は0.99)といいます。それでも「2.0」以下で人口減は進行中であり、「持ちこたえている部類」に入るわけです。
一方、全国の少子化対策です。報道によると異次元の少子化対策として来年度は3兆円半ばという予算規模を首相が指示したそうです。内訳は社会保障費等の予算を2兆円削減し、他に1兆円規模の財源を保険料に加えて(税金として)徴収するとされています。
丸山知事は、この子育て支援1人当たり500円を「人頭税みたいな大衆課税」であり、消費税とともに逆進性の高い不平等税制であると強く批判しています。1人500円均一という平等にみえるけれども「負担能力を見極めてはいない」不平等税制です。
そして昨年度大企業は純益で(いろんな支払いを済ませて残った利益)が41兆円あり、「そのうち1兆円を負担してもらうことがそんなに無理なことなのか」と提起しました。わかりやすい提案です。
丸山知事は、大企業の人にあうとほとんどが「SDGsのバッチをつけている。少子化対策で子どもが増えることは、日本社会のサスティナビリティ(持続可能性)をつくること、SDGsそのものであると訴えていました。
政府の「異次元の少子化対策案」は……詳しく述べる気がしないほどですが、「第3子以降は児童手当てを月額3万円に倍増する」といった具合で、ABEMA Primeの出席者が「これで子どもをもつこと気になるのか?」と嘆いています。
追加しておきますが、社会福祉費などを削減して、子育て支援費を捻出する(?)というのも、大いに疑わしい限りです。
一般に、女性の社会進出(就業率の増大)、高学歴化(進学率の向上)などにより出生率は下がる傾向があります。出席したパックン(パトリック・ハーラン)さんによると、「先進国で出生率を向上させるのに成功した国はない」といいます。子どもを持つことで、国に納めた税金を自分が取り戻せるいろんな施策があって、子どもを持つことがよい状態になれば…という考え方を示しました。現実の事態はそれとは反対方向に進行しています。
(註:年月、数値は聞きまちがえがあるかもしれません)
社会福祉の多様なミニサービス業
社会福祉のミニサービス業に注目「新聞好き」とでもよびたい人が気になる(?)記事を残してときどき私にも見せてくれます。全国紙が中心です。
いくつか概略を紹介します。2023年9月1日「朝日」のひと欄にある秋山正子さんは、2016年に「マギーズ東京」を始めた人です。元看護師で、末期がんの人に「早く相談に来ることができれば、最後の過ごし方が違った」と活動をつづけています。利用は無料で、のべ4万人が訪れたそうです。
2024年4月9日ひと欄で紹介された藤田淑子さん。同僚とフィランソロピー・アドバイザーを設立。富裕層が障害者やひとり親家族を支える社会貢献に携わる活動のようです。慈善活動の推進です。
2024年4月7-8日の2日連続で「毎日」に紹介されたのは「福祉専門官」。刑務所で受刑者が社会に戻るのを援助活動しています。「再犯防止に向けた最初の入り口を示す人たち」です。日付は不明ですが「東京」には「セーフティネット住宅情報提供システム」も紹介されています。多くの空き家がある一方で他方では入居が断わられる人たちもいます。その課題や活動を報じています。
これらの取り組みは個人有志の経験、得意なこと、思いつきを生かしたもので、必ずしも広範に展開されているわけではありません。事業体として成立しているものもあるし、不安定なものも多くありそうです。先進国といわれながら社会的格差の拡大、孤立・孤独など社会課題が広がる日本ならでは可能な取り組みです。
社会福祉分野として、保育や介護や障害ほど大きなニュースになりませんが、社会的サービス分野として注目できるでしょう。これらは相談サービス業です。必ずしも公共サービスとして大きく広がるともいえませんが、いろいろな形で生まれています。社会的弱者に手を差し伸べる国民の共感も得やすいし、それぞれの熱意を応援する取り組みになります。
この「新聞好き」の人は特定の目的を持って、このような記事を集めているのではないでしょうが、どこかに自分にも役立ちそうなことがあると集め、残してきたのでしょう。私はこのように発想しました。
コンビニは社会のインフラになっている
東京都大田区が区内のコンビニにAED(自動体外式除細動器)を設置するニュースが流れました。大手コンビニチェーンのローソンと契約し、他のコンビニチェーンにも広げていくようです。
隣の席にいるDくんによると今年は日本にコンビニが生まれてから50年ということです。コンビニは文字通り「便利」です。初めは生活日常品を扱うチェーン型の小売商店から始まったと思います。思い返してみると、コンビニによって違いはありますが、非常に多くの役割をもつようになりました。
銀行のATM(現金自動預け支払い機)、子どもなどの安全シェルター(逃げ場)、公共料金等の支払い、コピー機の設置、ネットと結びつくプリント機能、宅配便の受付、郵便ポストの設置、切手販売、臨時の公衆トイレ、店内軽飲食、特定不用品の回収ポスト……という具合です。ドラッグストアに近い役割のところもあるようです。
公共機関ではないですが、地域の人や通行者にも開かれたスペースの役割をもっています。調べると全国に5万店以上もあり、国民の生活には大いに役に立っています。小売業の歴史では戦後表われたスーパーマーケット以上の大きな特色をもった小売業種ですが、上に紹介した小売業を超えた性格を広げています。
課題はコンビニ店の従業員と経営者にこれらの負担がかかることです。特に深夜営業の継続、アルバイト・パート従業員の補充、いろいろな作業知識の習得、さらにカスハラ(顧客からの理不尽な注文)対応もある気がします。
24時間営業が大きな役割を果たしており、それを支える社会的対応を考えてもいいと思います。コンビニは将来の社会を考えるとき、地域コミュニティに欠かせない要素、インフラストラクチャー(生活基盤)に成長しています。それらを生かすために防犯設備や駐車場の監視カメラなどを公に補助をしてもいいと思うほどです。
私がよく行く近所のコンビニ(複数)では、中国人などアジア系の若い人が何人かいます。高校生など若い人のアルバイト経験などはよい社会経験になるのではないでしょうか。これらは日本社会に馴染む社会経験になるでしょう。
6月15日(土)、高田馬場で セシオネットネット親の会
来週の土曜日、高田馬場で セシオネットネット親の会 を開きます。
連絡は 松村淳子(090-9802-9328)さん、または松田 武己(03-5875-3730)にお願いします。
セシオネットネット親の会(東京都新宿区)
不登校・ひきこもりの親の会です。
6月15日(土)14:00~16:00(延長になることも)
毎月第3土曜日の午後になります。
場所は助走の場・雲:新宿区下落合2-2-2 高田馬場住宅220号室
高田馬場から5.6分です。
親世代の方の参加費500円(入会1000円)、当事者は無料です。
インド経済の「非公式部門」から考える
気になる記事がありました。インドで国政総選挙が実施中で、それに関連するものです。
インド経済は「非公式部門」(インフォーマルセクター)と称する部門があり、インド労働者の9割近くがここに分類されています。それは「靴磨きを含む露天商や建設現場の日雇い仕事、家事労働など、行政の指導を受けない小規模な経済活動」とされます。
ILO(国際労働機関)はインド労働者のうち、非公式部門に従事する人……は、「法律に守られず、低賃金や健康問題に苦しむ人も多い」といいます。紹介された靴磨きの人(24歳、首都ニューデリーの商業地区)は月15000ルピー(約28000円)で「生きるだけで精いっぱい」で、税金は納めず、社会保険にも加入していません。
気になるのは非公式部門にある「家事労働など」です。これは私が述べてきた無償の家事労働とは同じではないと推察されます。
途上国においては、市場経済の広がりが限定的で、自給自足的な生産(農産物、衣類などの生産)が広範にあり、廃品回収と再生、物々交換も多いと思われます。これらも「家事労働など」に含まれるのでしょう。
IMF(国際通貨基金)では、GDP(国内総生産)にこの非市場経済部分の活動をカウントしていると思われますが、その算出基準はどのようなものか。それは「家事労働など」を考える時の参考になるかもしれません。
記事ではまた次の点が紹介されています。
『時事通信の取材に応じた経済学者のアルン・クマール氏によれば、国内生産への非公式部門の寄与度は約45%。非公式部門のデータを迅速に把握することは困難なため、公表されるGDPには実態が適切に反映されていないといいます。
同氏は、「非公式部門」の効率は大企業を含む「公式部門」と比べて低いにもかかわらず、公式部門と同等と想定して推計データが算出されていると指摘。インドの経済成長率には「上方バイアス(偏向)がかかっている」と説明しました』
このような「非公式部門」は、いわゆる闇経済との境界が不明のところもあると思われます。闇経済につながる部分は途上国に固有ではなく、日本での「サービス残業」や汚職・ワイロ、さらには政界の裏金と似ているところもあり、他国の事情とは言い切れません。これらは市場経済の発展とともに解消のベースが広がるわけですが、自動的ではなく民主化の動きや情報公開の制度にも左右されるはずです。
紹介した記事で非公式部門はGDPの約45%を占めると指摘されています。「家事労働など」は私が問題にしている「無償の家事労働」(家庭内家事労働)と地続きでもあります。これは(IMFの)統計上どのように区切られているのか、あるいは区切られていないのか分かりません。日本の「家事労働」を考える参考になるのか、参考にならないのか…この点も注視点です。
インドのGDPは、数年内に日本をおい越し、アメリカ、中国、ドイツに次ぐ第4位になると推測されています。国民の豊かさの表わす基準で、たしかに1つの目印ではありますが、実態を見ると心もとないとも見えます。GDPを超える国民生活のゆたかさを計るより確度の高い基準は必要なのです。
この記事は、時事通信(ニューデリー発)のもので「しんぶん赤旗」(2024年5月30日)掲載によります。