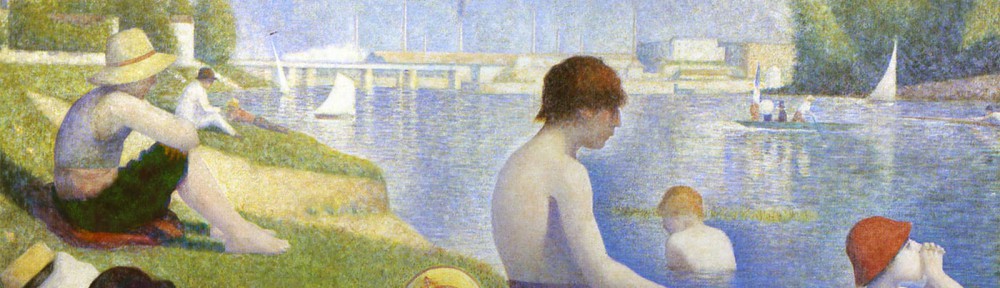夏休みを使い卒業生の親と懇談するために、九州からS先生が上京されました。
そのS先生としばし情報交換です。いろいろなことに及んだのですが、S先生が改めて印象強く思ったのは次の点のようです。
不登校情報センターは、通所している当事者に、特定の器を用意して、そこに進むような取り組みをしてきませんでした。一人ひとりの状態をかなりの期間よくみて、その人にあった器をつくろうとしてきました。
例えば、ある引きこもり当事者のところに訪問をし、自宅でホームページづくりを続けています。当初はその人も不登校情報センターにやってきて、その作業をすると何となく考えていました。いまはその状態を肯定的に見て、それを在宅ワークにするにはどうすればいいのかを考えています。
その鍵は、こちらで用意したホームページ制作の作業内容をつくる状態から、自分なりの発意や工夫を取り入れていく状況に進むことだと予測しています。
これがうまくいくかどうかはこれからのことですが、こういうものがその人にあった器をつくる方法ではないかと思います。不登校情報センターの不登校や引きこもり経験者の支援、それを大まかにいえば社会参加に向かうことです。
その方法には就職する道もあります。もし就職するつもりの人がいれば、センター内でどういう役割をしているかに関係なく無条件でそれを優先してきました。
仕事おこし型であればセンターとして何かできることはないかと考えてきました。情報センター自体を仕事のできる場にしようという要請には本当にゆっくりですが進めてきました。この他にも各人の様子や要望によるいろんなことをしています。
うまく行くものもあるし、うまく行かないものもあります。むしろうまく行かないものが多いでしょう。それでも予定した器に入るように進むのではなくて、その人の状態にあう器をつくろうとしてきました。それによりこれまで継続できたし、広がってきているのではないかと思います。
S先生の反応から、逆にこちらの特徴を感じました。