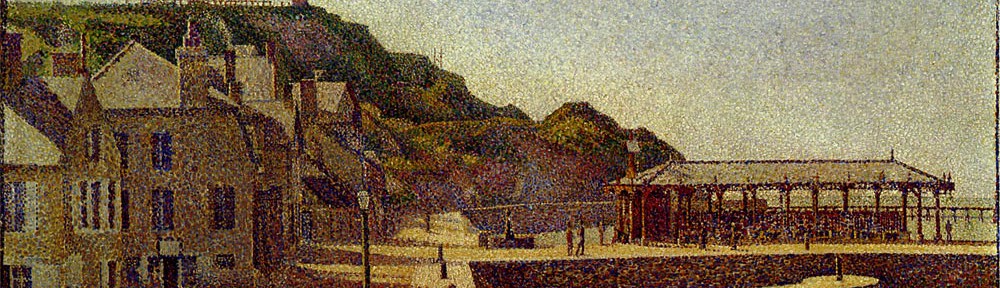シリーズ「なでしこ会講演その後5」です。引きこもり当事者への訪問活動をお話します。訪問活動の内容はいろんな面に及びますが私が到達した「選択的で了解的な訪問方法」の紹介にかぎります。
(1)訪問を始める前提として、引きこもっている子どもと親の間に何らかの会話ができる状態が必要です。親子が会話をできない状態で、訪問者がそれを超えて当事者と顔を合わせる関係になることはできません(役所関係のなんらかの手続きにおいてはありうるかもしれませんが…)。
(2)本人が同意または反対しない状態で、支援者が家庭を訪問し始めることが求められます。このための手順が要ります。この方法を「選択的で了解的な訪問方法」と呼ぶことにします。
家族と相談をうけて、いくつかの提案を考えます。それを箇条書きにして家族から当事者に示します。いずれも当事者の状態や環境条件にそった内容です。
たとえば、①親戚の××さんの所の仕事を手伝う、②パソコンを習う教室に通う、③訪問活動をしている××さんに来てもらう、④中学受験を目指している××くんの家庭教師をする、⑤親の会に当事者が来ているのでその人たちがいるフリースペースに参加する。
これらを5、6項目を並べ1週間ぐらいの期限付きで本人に選択してもらいます。1項目を空白にし本人の提示する方法も書けるようにすることもあります。期限内に答えがない場合は、「③訪問をしている××さんに来てもらう」にすると伝えておきます。他の方法と違い本人が動かず家にいてもできる方法だからです。
これらの提案をできる環境をつくるのにある程度の時間を必要とします。突然やってもうまくいく可能性は少ないものです。この方法をあえて「選択的で了解的な訪問方法」と呼ぶことにします。
(3)「選択的で了解的な訪問方法」に至るまでにはいろいろな試みをしました。これができた後も手続きを省略したこともあります。本人と顔を合わせることができる割合はこの方法が格段に高いと思います(私個人では累計で40人以上を対象に訪問活動をしています)。
それでも絶対的な方法ではありません。本人と顔を合わせてからが本当の訪問活動です。連れ出すことを優先すべきではありません。当事者がなぜ外出をできないのかの理解をしようとするスタンスが必要です。本人の状態・気持ちを理解しようとするなかで、どうするのかは本人が口にするのを待つのがいいと思います。訪問初日に「不登校情報センターに来ないか」と勧めてきた人もいますが、それは例外と考えるべきことのようです。
(4)しかし、自分がどうすればいいのかは当事者にはなかなか思いつかないものです。それ以前に関心のあること、意欲がわかないことなどを話し始める時期があります。それを聞きながら訪問者が体験したこと、見聞きしたことを話します。そうしなさいというものではなく、訪問者自身のこととして話します。小手先のことばでは空振りに終わります。当事者のことは当事者が考えるしかないのです。
訪問者には「選択的で了解的な訪問方法」を始める前に提案したことはここで参考になります。この時期に参考にならないことばかりを「選択的で了解的な訪問方法」のときに提示しているとここで行き詰まることがあります。ここでそれまでの訪問で気づいたことなどを参考に改めて考えることも必要ですが、スタンスはすでにその時点でわかっていなくてはうまくいかないと感じます。
訪問活動は長期の引きこもりへの中心的な取り組みです。とても言い尽くすことはできませんのでこのあたりにしておきます。「五十田猛の論文とエッセイ」にときおりその経験を書いていますので参照してください。