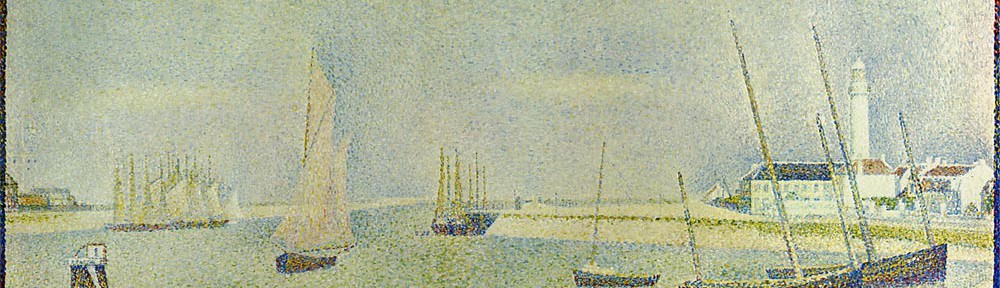自分で判断し動く(3の1)
臨機応変が苦手です。アスペルガー気質の人はそのように言われていますが、引きこもりの経験者もまた同様です。手元の『新明解国語辞典』(1996年、第28刷)には臨機応変とは、「あらかじめ決めた方針にとらわれず、その場合場合の状況に応じた対処をすること」と説明されています。
私が見る範囲でもそのような引きこもり経験者は多いと思います。
しかし、これはやや極端な状況を指しているのであって、日常的にはもっと頻繁に現れている現象があります。
ある流れのなかで続いていることに対して、自分でどうするのかが決められないのです。既に決まったやり方、指示されたことはかなりできるレベルの人はいます。しかし、自分で受けとめ、判断し、次のどうするのかが苦手です。受身の姿勢といわれるものです。
臨機応変が苦手というのは、事態が急に変化したときに使われますが、ゆっくりと予想できる範囲のことが続いてきても自分でどうするのかが苦手、出来ないのです。思考停止のように感じます。
長期の引きこもり経験者が社会参加する困難さの相当部分は、ここに由来するものと考えています。幼児が話すとき「たのしかった」というのをたどたどしくいう子がいます。あの状態が長期化した引きこもりには続いているかのようです。「のろのろ全速力」、自分では全速力、剛速球で動いているのですが、実にゆっくりとしていることになります。仕事に就いたときに、“テキパキ”、“キビキビ”といわれるのです。神経系統の成長が停滞しているのではないでしょうか。
神経系の成長は全人的な成長の一部です。ことに対人関係の空白はこの脳神経系の成長の停滞を招いているのではないかと思います。
引きこもり居場所だより
不登校情報センターのワークスペース、居場所、相談、親の会、ミニイベントなどの様子をお知らせいたします。2014年1月、不登校情報センター・センター便りの名称変更です。