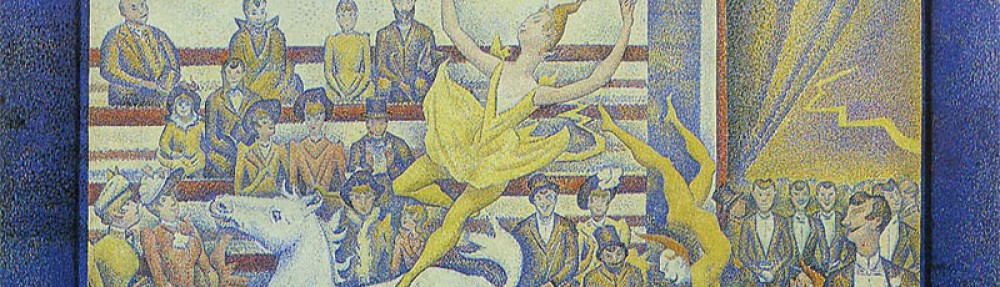シリーズ「なでしこ会講演その後6」です。支援者にも訪問サポートをする人も、また家族に対しても私は引きこもりの当事者を理解しようとするスタンスが重要であると述べてきました。
こういう人の多くは引きこもり当事者の感覚を理解できないと思うからです。何によって理解するのかと言えばイメージとしての理解、理論として理解にとどまり、それは本物の理解と同じではありません。
ここに書く内容は、次の質問への回答です。
②《親子の会話が全くない場合の対応法についてどうしたら良いのか知りたい。》
③《全く会話もなく部屋から出てこない娘に、どういうきっかけが良いか教えてほしい。》
この背景には、当事者の言うことがこれまで理解されてこなかった長い経過を感じます。引きこもり当事者たちは、理解されてこないことを通してある種の絶望やあきらめに至ります。それが家族との深い断絶です。質問者のように同じ家に住みながら家族と断絶状態にある人は少なくないと予測できます。
引きこもりのかなり多数は、繊細な感性の持ち主です。一般人が感じないものをとらえる人です。感覚のよさによって自分が周囲をとらえたことを他の人がわからないのをむしろ不思議に思います。この長期の蓄積の1つの結果が対人不信であり、対人関係の距離感が取れなくなる事態です。
ある人が、自分の周りにいる一般人の感覚を持つ人を「向こう側の人」と呼びました。引きこもりを何らかの身体・精神の不全状態と考えているのとは逆に、その繊細な感性をもつ人からは一般人は「向こう側の人」であり、事態をよくとらえられない人なのです。
この溝をことばでは埋め尽くすのは難しいほどです。どういうことかと言えば、青という色をことばで表現をして隣の人にわかるように説明してください。目という感覚器では青はすぐにわかりますが、それをことばで伝えることは至難のワザ、たぶんムリでしょう。
同じように周囲にいる人の雰囲気を感覚として深く受けとめることができるのが繊細な感性の持ち主です。この感覚をことばで伝えることは難しいのです。それは自己防衛、自己保存と結び付いたものです。幼児が周囲の人の雰囲気を感じ取る能力に似ています。
このように感覚をことばで伝えることはかなり難しいのです。せいぜい理解しようと努める、イメージできるものを持ってくる、実例を挙げてたとえてみる、それにより両者は接近することができます。これを私は理解しようとするスタンスを持つことと考えたわけです。
よりわかっているのは引きこもっている当事者なのです。一般人である親は実は見えていない人、わかっていない人なのです。支援者や専門家の多くもまた感覚においては一般人と同じです。わからない人がわかる人に対して支援とか指導というのです。おこがましくはないですか。
わかっていないがゆえに平気でいられるのです。それが社会生活のできる理由です。こういうと極論になるでしょう。社会生活が通常にできるには、少々の不都合が周囲に巻き起こっていても、それが自分の活動にはなんら支障を及ぼさないだけの力量、精神力、社会力を備えているのです。自己防衛をそのような能力に置き換えてきたのです。
それが備えられていないという意味で、社会から身を引いた状態が引きこもりなのです。繊細な感性が成長のじゃまをしているともいえます。それを否定的に考えるのではなく、それを長所として生かすなかにこれからの可能性が見つけられるでしょう。しかし周囲に理解者が必要です。
質問者への答えは、聞く耳を持って、聞くスタンスをもって理解しようとし続けることです。当事者が話している途中でさえぎらない、終わりまでよく聞く、そういうことを続けていくとやがて相互の会話が成り立つようになります。その後はその時点で考えるのがいいと思います。このシリーズの4(親の会)、5(訪問サポート)が直接的なものですが、基本的には3(社会的な状況)であり、当事者自らがそれを感じて動き出す可能性が大きいと思います。