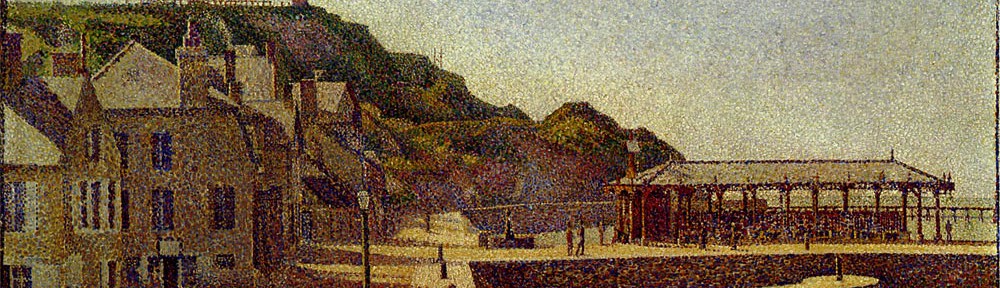金子隆芳『色彩の科学』ノートで私は引用を省いたところがあります。「第3章 ヘルムホルツ三色説」の第1節「感覚神経の特殊エネルギー説」の一部です。
「ニュートンは…眼に入った光は視神経を波動のような形で伝わって行き、大脳のセンソリウムに到って光や色の感覚になると考えた。…」(37ページ)「この問題について一つの解決を示したのが、ヨハネス・ミュラー(1801-58)の感覚神経特殊エネルギー説であった。ミュラーによると、視神経とか聴神経といった感覚神経を伝わるのは、もはや光や音の波動のような物理的エネルギー、あるいはそれに類似したものではない。神経には神経固有のエネルギーがある。
そのような神経エネルギーへの変換は、視覚の場合は眼の網膜で行われると考えられる。ミュラーは何を考えたか知らないが、現代の神経生理学の定説によれば、神経の活動は電気的パルス説である」(38ページ)。
引用は続きますが一休みをして、註と私見を入れます。
*センソリウムとは、「大脳の感覚中枢で、そこで感覚が意識になる」(22ページ)。
ミューラー説を『色彩の科学』も現代の神経生理学の定説も否定しています。私が「精神エネルギーの消費と肉体エネルギーの消費には違いはなく…」といったのはこの否定説によります。しかし「ミュラーは何を考えたか知らないが」といいますが、意外に意表をつくことを考えていたのかもしれません。
「その活動がどのように『特殊』かというと、その原因が何であれ、例えば視覚神経の活動は視覚体験しか起こさない、聴覚神経の活動は聴覚体験しか起こさない、ということである。もし眼を電気で刺激しても、その電気が視神経を伝わるわけでもないし、ましてや『電気』を見るわけでもない。私たちは光を見るだけである。聴神経だったら音を聴くのである」(38ページ)。
この後、次の文章を私はノートしています。「特殊エネルギーの種類は感覚の種類だけある、例えば視、聴、味、臭、触の五種類としておこう。そして、『それしかない』。感覚神経のそういう特殊エネルギーの限定のゆえに、われわれは外の物理的世界がどうあれ、天から与えられた神経エネルギーの五つの様相でしか世界を知ることができない」(39ページ)。
ヘルムホルツはミューラーの弟子の1人であったが、『生命といえども物理化学的過程であるから、物理化学的法則で説明すべき』として「筋肉の代謝の問題からエネルギー保存則をたてた(1847)。人間も熱機関と同じだということである。こういう人間観だからミューラーの生気論を批判するのも当然である」(40ページ)。
『色彩の科学』はこのようにミューラーに代わるヘルムホルツ説を紹介しました。私はこれを受け入れます。それでもミューラー説の未知の部分も知りたいし、「感覚神経のそういう特殊エネルギー」の研究により現代の神経生理学に新たな意見表明はないかと気にしているのです。
16日の「精神エネルギーの消費と筋肉エネルギーの消費は違うか?」で書いた次の2点はそれを意図的なテーマにするものです。
(1)筋肉の代謝とは筋肉を動かすエネルギーと同じに取っていいことなのか。
(2)パルス波の1つひとつのエネルギー量は同じとしても、精神エネルギーの消費と肉体エネルギーの消費の問題を扱ったことにはならないのです。
「小難しいことを書いてわからない」という意見を聞きましたので、しばらくはこの問題はブログから離すことにします。