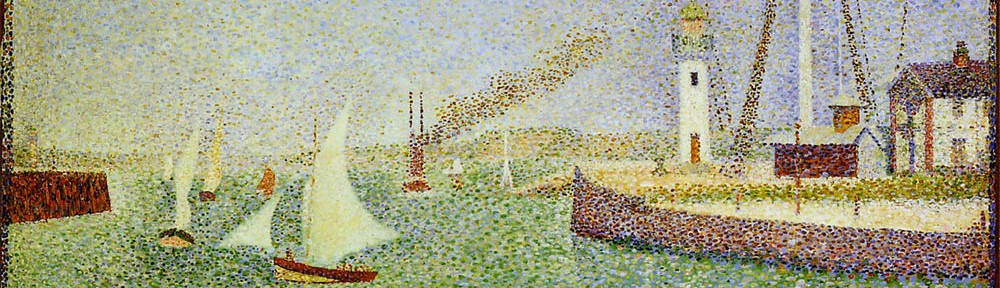1月20日、愛知県武豊町で「長期化する引きこもり支援活動」として講演することになっています。講演の要綱をまとめました。大きくは2部にわけ、前半は不登校情報センターの取り組みの経過、後半は当事者の状態と居場所の役割です。主催のなでしこ会に送ります。講演の当日までにさらに検討していくぶん違うことになるかもしれません。
〔Ⅰ〕不登校情報センターの就業の取り組みの経過
(1)ワークスペースの始まり
いまから10年ほど前に、通所していた当事者から不登校情報センターを働ける場にしてください、という声が聞こえるようになりました。当時、30歳前後の人の会という15人ぐらいのグループがあり月2回ほど話し合いをしていました。私はほとんど参加しなかったのですが、2年ほどすぎて話し合いだけでは行きづまりを感じたようです。
①当時は引きこもり経験者とはいえ10代から20代の人が多くて、30代以上の人は少数でした。それだけに「これから働けるようになるかどうか」の問題が切迫していたように思います。
②一般企業で働くには困難が多くて、その道は選べないと判断。何人かはアルバイトなどで働いた経験があり、そういう経験に基づく意見交流だけに状況判断は根拠があります。
③居場所が第2の引きこもりの場所になる、引きこもったままで社会参加をしたい、そういう意見も検討し、そのうえでの要請でした。
④こういう背景から出された要望でした。私は起業家ではありませんでしたが、何度かの話の中で「不登校情報センターを当事者にとっての収入になる取り組みを始める」方向を答えました。それが今日のワークスペースの始まりです。当事者の会という居場所を土台にワークスペースが生まれたのです。
(2)収入になる取り組みの広がりとサイト制作への集中
①実際に収入になる取り組みにしたのは、
*内職(ストラップの部品作りでしたがすぐに断念)、安くて、時間がかかりやってられない。
*ポスティング(ぱど=月2回と月刊新聞で2006年まで続いた)、1地区からはじめ4地区(3500部)まで広がった。参加者も多いときは15名を超えたがその後、参加者が減った。また新聞社は倒産した。
*DM発送作業(2011年まで年2回程度)、リーマンショックと3・11地震のあとに参加校が減り、収入が減り、自前の取り組みが難しくなった。しかし今年また企画して欲しいという要望がきている。
*テープ起こし(2004~06年)、できるのは1名。
*ヘルプデスク(2004~07年)、一時は多少あったが、いまは1名が細々と続けている。
参加者が安定しない(関心、出来ること)、基本的に収入が少ない、継続的なものに応えきれない、などの複合的な原因で途切れていきました。
②ホームページづくり
不登校情報センターの本来業務は学校や支援団体の情報提供⇒その方法が本からネットへの移行していきました(2004年)。
*作業チームづくり(2004年の数名)から体制づくり⇒NPO法人(2005年)にし、目標を「パソコンを収入源にする」。パソコンの獲得と整理(ほとんどが中古のもらい物)。
*収入項目の企画・設定⇒大きなサイトを構想し、項目別ページを企画し、ページがある程度できたところから掲載料、リンク料、広告料を導入、そのご掲載料を無料に。作業費の支払い基準づくり。
*作業チーム、最初は1、2名のできる人から始める。
2006年秋に作業参加可能者の会合(10名くらい参加したが継続した人はいない)。
4台のパソコンで週3回実施チームが動く(2007年春)。
Wikiシステムの導入(作業に参加できる人が10名程度に増える)。
サーバーの統合とアドセンスの導入(2011年)⇒ネット自体が収入になる仕組みを強める。
現在はノートを含めパソコン7台が“稼動”。
③パソコン関係以外(ベースキャンプとしての居場所)⇒〔Ⅱ〕につづく
*創作活動:2006年2月第1回、2011年5月第5回。創作品の販売はホンの少々。
*メンバー個人の対人サービス業中心の取り組み:2011年秋から始める。ヘルプデスク、メイク、居場所案内、手紙相談サポート、訪問サポート(トカネットへの参加)、体験発表企画、ブログの運営…。
(3)ワークスペースの到達点
①週4日のワークスペースが回転している(各自の作業を分担)。参加者は10名程度。他に作業に加わらない人が数名、センター内のイベントには参加する人も別にいる。
1人あたりの作業時間は月数時間から60時間で個人差が大きい。
②各人の収入レベルは数万円。ただし、情報センターとしての収入が追いつかず合計100万円程度の未払いが発生している。アドセンスはほぼ予定レベルに到達。これを倍加するのが今年の目標。
③在宅ワーク(出張オフィス)の開始(2013年から。成否はこれからの動向による)。
(Ⅱ)居場所⇒(観察・要望・企画)⇒ワークスペースの役割
(1)社会参加促進団体の3タイプ⇒学校型、福祉型、仕事起こし型(集団的なSOHO)のなかで活動スタイルを(集団的なSOHO)に位置づける(2005年)。
(2)3つの特徴点(作業が遅い、休み時間が多い、臨機応変と責任の回避⇒集中可能な時間に左右される:個人差は大きい)に見合う作業方法をつくる。
(3)パート労働の3つのパターン:バイト等の就業者の経験。
①3か月のフルタイムバイトと数か月の休職の繰り返し。
②週5日・1日2~3時間の短時間バイト。
③週2~3日のフルタイムバイト(2週で5日制もいる)。
*これを超えると心身状態がおかしくなることが少なくない。「無理をするな」(自分の体調を自分でよく知る、短時間バイトの繰り返しを通して自分を状態を知る)。
*集中力の限度(オーバードーズのTnさん⇒親に言ってもわからないので、体の状態で表わす)
(4)好きなことを仕事にする積極性
①仕事はできないが、趣味のネットゲームは休まない、釣りはいつでも元気、創作活動はしている…。
趣味などは精神的疲労感や不安が少なく継続できる。それを収入にする条件を探しつくる。
②個人事業的なものが適している。SOHOであるが個人単独ではできないので集団的で支援者が関わるワークスペースがあるとやりやすい。高い山に登るときのベースキャンプのような役割。
③コピー機、パソコン、宣伝、イベントなど事務、企画、広報と当事者間のつながりがバックボーンになりやすい。
(5)社会的・制度的支援を要する背景
引きこもり経験者の就労条件はいくつかの特殊条件があります。また個人差が大きく一人ひとりの状態に例外として対応する環境が求められます。
それでいて事業所としての経営が成り立たないと継続ができないものです。社会的・制度的な支援を要するのはこのためです。
①「引きこもり」認定制度、または「引きこもり支援事業所」の認定の導入。
②将来の住宅・生活条件を含む社会的な環境整備をめざす取り組み。