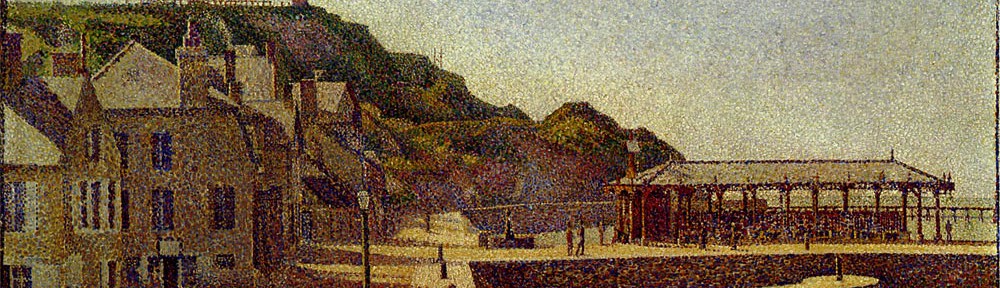上のテーマで方針をまとめました。要点を公表します。
「パソコンを収入源」にする姿が、イメージできるようになりました。
情報社会とよべる社会の到来が迫っていることが前提の一つになります。主体的にはサイト制作レベルが向上し、この方向に可能性を感じられるまでになりました。いまは到着する前の先行投資を要する苦しい上り坂の時期です。
4月から採り始めたいくつかの措置と方向を基に説明します。
(1)詳細情報の掲載とリンク
学校や支援団体の紹介ページ(詳細ページ作成)は、無料にしました。
(2)広告表示と収入源
広告を「小分け」し、多くの学校・支援団体に提示します。
トップページ以外にも(“ネクストページ”、イベント情報ページなど)より低価格の広告設定を提示します。情報社会に対応した収入源は、多数の取引先(学校・支援団体)からの収入、ネットショップによる通信販売になります(ネットショップの展望を語ることはまだ不可能です)。
(3)高レベルのサイトの充実を図る
①SEO対策と周辺
ページ全体を充実させ、信頼性の高い、利用のしがいのあるサイトをめざします。ページの充実には、掲載情報の豊富さ、リンク・被リンクの多さも含まれます。SEO対策を技術的なことに限定せず、ページ全体の充実によるものとします。
。
③学校・支援団体以外の情報の豊富さ
親の会・当事者の会の情報紹介にも特別のサ-ビス提供企画を考えていきます。
3月に実行した「引きこもりと保健所」は大きな成功を収めた企画でした。
サイト内の当事者ブログ、支援者(協力者)ブログを増やします。
④「イベント情報」ページの特別の役割
「イベント情報」ページを不登校・引きこもり・発達障害という専門分野における確実な情報告知に成長させることを目標にします。「少なくとも不登校情報センターのイベント情報には載せる」学校・支援団体が10か所以上はほしいところです。
⑤サイト内の見よさ・わかりやすさ
膨大な情報提供のデータベース型サイトであり、双方向をめざす意見交流型サイトです。
昨年12月6日に不登校情報センターを「引きこもりに結びつく当事者と支援者の情報交流ステーション」と再定義しました。この実現のために協力できる当事者・支援者の参入しやすさも図るつもりです。
サイトの内容は大きくなりますが、できるだけ「見よさ・わかりやすさ」も追求することになります。
「ページ説明とページ構成」というサイトマップに相当するガイドを設定したのは改善策の一つです。「新着・更新」ページも利用します。このページはアクセス件数が少なく、即効は期待できませんが、アクセスは増える傾向です。新規・更新ページに案内しています。またサイト内ページ群の説明をします。
(4)共同のウェブサイト運営業に向かう
不登校情報センターの学校・支援団体の情報提供は相手先サイトにリンクする方法だけではなく、独自に相手先の詳細情報を作成しています。情報提供業は相手先の情報発信をカバーする役割があります。相手先の情報を相互に比較対照しようとする利用者の利便性を図る役割があります。所定の情報提供用紙に基づく詳細ページ作成はここに関係します。
このような作業を積み重ねてきた結果、現在のサイトは情報提供型からウェブサイト運営型に移行してきました。より細かくいえば「ウェブサイト運営による情報提供型」から「情報提供を主とするウェブサイト運営業」に移行しつつあります。
情報提供型は広告業に近く、情報提供側から収入を得ようとする性格があります。ウェブサイト運営型は、情報提供側からの収入に代わり“不特定の”サイトの利用者が収入に貢献するようになります。サイト性格のこの移行・変化は情報社会への対応の仕方です。新年度の措置はこの移行をさらに一歩進めました。
(5)メールの利用を日常的に
学校・支援団体等への連絡・依頼などをメールで行うように移行します。
① 利用する分野
情報提供依頼、情報更新の案内、リンクの依頼、広告設定案内、イベント情報案内など。
②準備すること
情報提供用紙等をサイトに掲載しダウンロードできる形をつくります。
学校・支援団体等のメールアドレスを収集し分類・整理して保管します。
③可能性のある効果
サイトへのアクセス件数の増大。
(6)引きこもり経験者の企画の応援
以上は、引きこもり経験者の共同のワークスペースとして役割です。それ以外にもフリースペース・ワークスペースとしての役割があります。
①創作活動とネットショップ
*創作活動をする人の作品展示会、交流の機会、作品を販売する場を企画します。
*作品および加工品の販売はネットショップ設立に向かいます。ネットショップ自体の運営からみると、関係する当時者の作品づくりに頼っていては成り立ちませんから、独自の工夫と対策を考えなくてはなりません。
*読み終えた本、寄贈を受けた本などの販売コーナー、リサイクルショップ・フリーマーケットの要素をネットショップ内につくります。
②当事者の仕事づくり事務所と応援
*「チョコシゴ」への応援。
*「カラーセラピー」の実演スペース。
*「発表会」の企画応援。
③その他の引きこもり経験者のための活用への開放
*「引きこもり後を考える会」の応援。
*「トカネット」と学生サークル。