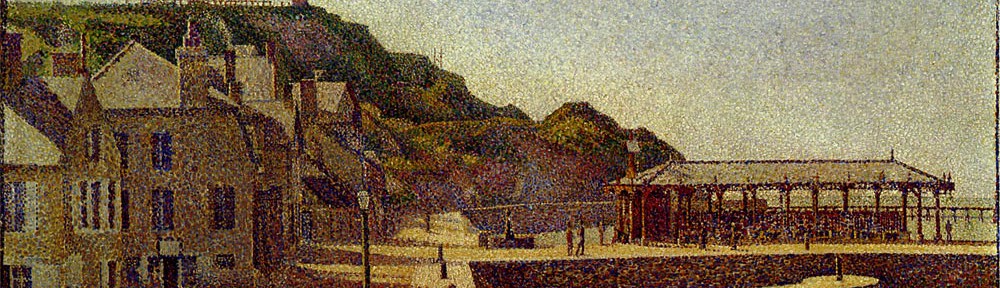10月2日の「引きこもり後を考える会」第4回では多くのことを話しました。
話した内容を数回にわけ、参加した1人として感想や意見を含めて掲載していきます。
その第1回は10月16日の「引きこもりから抜け出す」体験発表会に関して明瞭になった点です。
今回の発表者は架空のつくりごとでなく,現実に到達したことの発表になります=嘘はないのですが参加者にどの程度納得してもらえるのかは未知数であり、やってみないとわかりません。
当日のタイムスケジュールなどは3日の「創作者の交流会」の意見を聞き、様子を見て最終的に決めます。各人の発表時間は15分から20分程度です。その時間のなかで何を話すのかは各人で的を絞り、考えてください。
その後の相談時間に発表者は相談をどう受けるのか、発表者以外の相談者はどうなるのか、について松田試案を説明しました。
相談を受ける人は、発表の4人を中心に次のメンバーで調整中です。
(1)メイクセラピーを発表するSさん=女性(引きこもっていても)には訪問もできる。
(2)整体師を目指すOさん=引きこもりからどう抜け出したか、なぜ整体師なのか…など。
(3)NPO法人FDA=IT企業設立の就業支援。
(4)「引きこもりでも彼女ができる」Nさん=親とは手紙で継続的にやり取りしたい、仕事をする状況での話しなども。
(5)ヘルプデスクのHさん=参加できるか不明。案内チラシを配る。
(6)編み物教師のSさん=参加できるか不明。案内チラシできている。
(7)訪問サポート・トカネット=訪問サポート相談。
(8)不登校情報センター・フリースペース松田=パソコン教室、ワークスペース、自宅でのサイト制作などいろいろ。
この他にも相談を受ける人が出るかもしれません。
「引きこもりから抜け出す」体験発表会は、今後も繰り返し、そのつどテーマを変えていきです。親とともに当事者が一人でも多く参加をして欲しいものです。それにはどうすればいいのかを考えてみました。
内容の充実にかかっていると思いますが、それは参加してくる人の気持ちや状態にマッチしている取り組みであることは確かでしょう。発表者は自分のことで精一杯かもしれませんが、企画者はいろいろな状況の人の話を聞き、相談でき、参考にでき、協力できるようにしていきます。