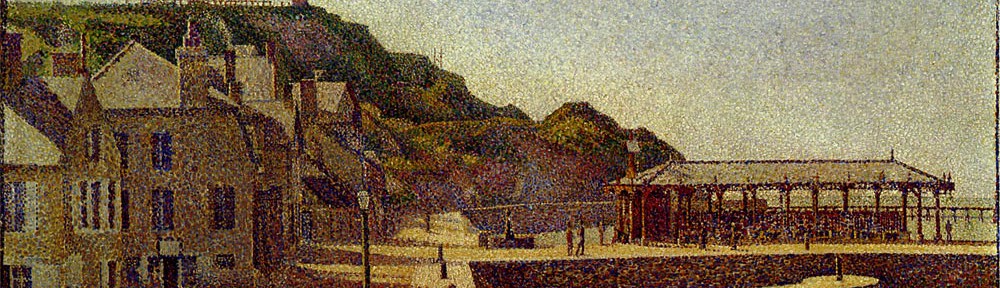昨日の“支援のスタンス”の続きです。
それなりに精神症状が重いと思える人(Aくんタイプ)には、顔を合わせたときに緊張感を下げ、その気持ちを楽にしように心がけてきました。そうするとAくんタイプには少しずつ依存をしてくる人が出ます。精神症状が重いこととは、子ども返りしやすいことにもなるのでしょう。
ところで依存をさせるのはよくないと言われます。本当でしょうか? 私の経験からはそれは相手によるのです。人間は(たぶん年齢に関係ないが…)依存を経験することで、依存から離れて自立に向かうのではないか。依存の経験がないまま、自立に向かうのは表面の仮の姿で、表面化させずに内に抱えているのではないかと考えたいです。
不登校情報センターに来るほとんどの人は子ども返りすることも極端な依存的な状態を示すこともありません。自分である程度切り上げながら自立に向かっているものと思います。もしかしたら表面的な自立を装いながら生活する、それは多くの人がそうしているのかもしれません。
しかし、Aくんタイプの人、日常生活に支障が出るほどの精神的な困難を持つ人は、それでは自立の道は閉ざされます。こういう極端な状態は、しばしば本質的に必要なことを明らかにするものです。「人は依存を経験することで、依存から離れて自立に向かう」ことが本質的なことと思うのは、こういう人に正面から向き合ってみないと実感できないのです。
私が“支援者として関わっている”と認めるのは、私に精神的な依存を示している2、3人です。この状態は私の日常を少しは制約しますから、あまり増やせそうもありません。しかし、人数が少ないにもかかわらず、振り返るとこの人たちから学んだことは私に理解の最大部分を占めます。
まだわからないのは、年齢の近い者同士だったらどうなるのかです。AくんとB君の例はここを考えさせてくれるかもしれません。
引きこもり居場所だより
不登校情報センターのワークスペース、居場所、相談、親の会、ミニイベントなどの様子をお知らせいたします。2014年1月、不登校情報センター・センター便りの名称変更です。